2019/10/02
2019年10月の予定
2019年10月のなつめやの予定
10月というのに30度を越す日が続くようなスタートで
始まりました。
9月には一旦、20度行くか行かないかの温度になり、
その後残暑のような暑さが続くようになりと、今年の
自然条件、お天気は厳しいですね。
そんなこともあってか、体が疲れやすい、という方も
多く、さらにこの時期には珍しくインフルエンザが流行しています。
空気も乾燥し、ウィルスも飛びやすく、同じウィルス性疾患の
風疹も、ちらほらニュースで取り上げられるようになってきました。
天候の不安定さと、夏の不養生が重なると
疲れやすい、というよりもそのまま体調を崩してしまう。
ここから先の秋・冬というのは夏の間の養生の底力が見えてきます。
冷たいものを飲食せず、早寝、を心がけましょう。
また、空気が乾いてきていますので体の中から潤すような
食材をできるだけ積極的に取り入れていくことも忘れずに☆
参考:『秋の乾燥は甘酸っぱさで潤す』
『夏の終わりに体調を整えておく 1』
『夏の終わりに体調を整えておく 2』
なつめやの10月の予定です
☆店休日:2・3・9・10・16・17(水・木)
23・30(水)
☆臨時休業日:12・18・22
☆薬膳養生講座:カネマツ倶楽部さん16日11:00〜
今月はぬか床を仕込みます

2019/09/30
消費税につきまして
消費税につきまして
本年10月1日より消費税率が8%から10%へ変更となります。これに伴い、なつめやでも10月1日に販売商品の消費税率を変更致します。
また、軽減税率制度の適用により、飲食料品については10月以降も税率8%にて
販売致します。ハーブティー、黒豆茶、食品などがこれにあたります。
漢方薬、医薬品、衣料品、雑貨類、また発想に伴う送料は税率10%となります。
ご不明な商品についてはお気兼ねなくお問い合わせ下さい。
お支払いにつきましても、なつめやでは現行のまま現金でのお支払いと
させていただきます。
ご理解のほどをお願い申し上げます。
なつめや 柏崎
2019/09/01
2019年9月の予定
2019年9月の予定
お盆が過ぎると急に涼しくなり今年は足早に秋が訪れそうな気配。暑いといえど、およそ2週間ぐらいで終わってしまいました。
どうしても、冷房に頼らざるを得ない時期がありましたが
それと同時に飲食で内臓を冷やしてしまっていて
お腹の調子が今ひとつだったり、疲れやすかったり、
腕の痛みや肩こりがあったりと、不調が少しずつ現れている方も
見受けられます。
『暑い』という時期は過ぎましたので、ここからは冷えた内臓を
回復するように飲食を見直し、体の疲れを取るために
早寝を心がけるようにしてみてください。
この時期の無理は秋から冬にかけての風邪、特に喉風邪や
インフルエンザなどの流行感冒に影響してきます。
腹巻きをしたり、出かけるときは上着、ストールなどをお忘れなく。
喉が乾きやすい、肌が乾きやすいという方は
卵、がオススメ食材ですよ。
不足している体液や血液を補い、体を潤す効果があります。
疲れやすい、虚弱体質の方に元気を与えてくれます。
また、から咳、のどの乾き、声がれ、気持ちの不安定感
などにも良いとされています。
特に女性は月経前後に乾きやすくなる方は召し上がる機会を
増やしてみてくださいね。
今月のなつめやのお休み
・毎週水・木曜日がお休みとなります
・臨時休業日:16日・23日
今月の講座
・23日:上田 Soin cafeさん 気功ワークショップ『気めぐり気功』
・25日:上田 アリオさん 女性のための気功養生講座
今月は上田での講座が2回あります。Soin cafeさんは初めての気功の講座になりますが
どなたでも気軽にご参加ください。気功の後はお茶をお楽しみくださいませ☆
また、その日は上田のトココトのイベント日でもあります。
様々なお店で独自の催しをしていて上田の街中を楽しんでいただくのも
良い1日ですよ。
2019/08/01
2019年8月の予定
2019年8月なつめやの予定
今年は梅雨明けが7月の終わりとなり
その後に早速猛暑となり、ジメジメ〜から激アツ〜に気候が変化しました。
体がむくんだり、めまいや吐き気、重だるさに悩まされた梅雨から
ほてり、動悸、イライラ、眠りが浅い、といった夏の体調変化が出てきます。
いらいらと怒りっぽくなったり、と言うのは分かりやすい変化かもしれません。
(普段からイライラしやすいと分かりにくいかもしれません・・・笑)
それは人の心身だけでなく、自然界がそのような状態なので
どの人にも起こりやすい状況ですから、互いにイライラしていると
余計な争いに発展しかねませんね。
自分の中にある『火』のエネルギーの発揮の仕方が大切です。
秋以降、涼しくなってからやりたいこと、やろうと思うことなどを
しっかり計画したり、基礎体力をつけるなどしておくといいですね。
涼しいうちの朝夕のウォーキング、気功、ヨガなどがオススメです。
本来なら夏にそのエネルギーを思い切り発散した方が良いのでしょうが
この暑さでは発散しすぎて、その後に疲れ切ってしまいかねないので
そのバランスを取るように心がけたいところです。
「遊んだらしっかり休む」
夏は五行では『火』、五臓では『心』
五行では夏は『火』に象徴されるので、火がメラメラ燃える様な感じのことが
心身に起こりやすくなります。
そして、五臓では『心』に属するので身体変化としては精神や心臓の働き
そのものに現れやすくなります。動悸や不眠、といった身体変化は『心』の
働きによるものです。
心の液は汗ともいわれ、汗のかきすぎは心に負担をかけてしまいます。
心が疲労しきってしまうと、いわゆる西洋医学的に言うなら
虚脱、熱中症といったことになります。
ここで一つ注意しなければならないのが、いわゆるぽっちゃりさんの
汗かき傾向。ぽっちゃりさんは水太り傾向であるのと、代謝が低い傾向が
あります。汗をかいているから代謝が上がってダイエットできる〜、
と思うかもしれませんがそもそも溜まっている水が多いのと、
水が多いために体の芯は冷えている、ことが考えられます。
冷蔵庫の中から冷たい飲み物を外に出した途端
水滴がつく、そんなイメージです。
体が冷えていると、滝のような汗が出てくる、と言うこともあります。
かと言って水を飲まないでいないわけにはいきません。
冷たいものをがぶ飲みせず、常温のものか
冷蔵庫から出してしばらく経ったものをこまめに飲むように
すると良いです。
また、酸味のもの、レモンや梅などが入った飲み物は汗のかきすぎを抑えて
心の働きを助けてくれます。
夏の食養生・生活養生
心に余分な熱をこもらせないようにするためには苦味のものや夏野菜が
欠かせません。手軽に摂取できる苦味はやはり緑茶やコーヒー、ゴーヤ
などでしょう。
夏野菜のトマトやナス、キュウリ、などは体を冷やしてくれますが、もともと
冷えやすい方や、下痢気味な方は食べ過ぎに注意し、できれば生姜やシソ・みょうが
などと組み合わせると冷えによる胃腸の働きの低下を予防することができます。
暑いからといって夏野菜をバリバリ生で食べたり、コーヒーなどを氷などを入れて
冷房の下で飲食などしていると冷えすぎてしまうかもしれません。
熱と冷えの関係では熱は上昇しやすく、冷えは下降しやすいと言うのは
自然界の摂理です。
人間の体も同様に頭はのぼせたように熱くなりやすく、
下半身は冷えやすくなります。
上も下も同じくらいの温度であればバランスよく対流していますが
下半身が冷えれば冷えるほど頭は暑く、のぼせやすくなります。
飲食で冷やしてしまうと同様のことが起きてしまい、
冷やしても冷やしても暑く感じるわけです。
できれば、頭だけ冷やすのがよく、アイスノンや冷えピタ、
濡れタオルなどで上半身や頭を冷やして、お腹から下は
冷やさないようにする。
暑くて冷房などをつけっぱなしで寝てしまうと
体が冷えてしまい、外の暑さと体の冷えの温度差により
汗をかきやすくなったり、夏バテ傾向が出やすくなります。
寝るときはアイスノンをお勧めいたします。
夏の暑さは体質改善に一役買う
今年の夏は長くなるのか、あっという間に過ぎてしまうのかは分かりませんが、
夏が暑くなくては作物は育ちませんから、この暑さは自然界にとっては
必要な暑さであり、私たちの体に取っても必要なことです。
夏の暑さによって、しつこい体の中の冷えを改善することができますし
体の中に溜まっているものを汗で発散することもできます。
冷房や飲食物で冷やし過ぎてしまうと冷えを改善するどころか
冷えが悪化しやすくなり、また、体の中の老廃物もたまりやすくなります。
(特に汗腺に近いところの老廃物。肌ですね)
去年は猛暑でガンガンクーラーを使っていましたから
秋以降、インフルエンザが大流行でした。
風邪などは東洋医学では『肺』の働きが低下したために
生じやすくなると考えられます。
汗をかくことで肺の働きが活発になり、免疫力を上げてくれます。
夏の過ごし方はそれに続く秋・冬に大きく影響しますので
どうぞみなさま、冷やし過ぎず、暑過ぎず、
楽しく夏をお過ごしください。
さて、なつめやも夏は少しお休みが多くなります。
なつめやの休み・行事予定
毎週水曜日定休日:7・14・21・28日
その他の臨時休業び:1・4・12〜15はお盆休み・22・29
講座:21日カネマツ薬膳講座
*新規予約が2週間前くらいからお取りすることが
できます。直前などはお取りできないこともあります。
また、直接お店にご来店いただきましても、ご予約の
お客様がいらっしゃることがありますのでお話をお伺い
できないことがあります。
ご了承ください。

2019/07/02
2019年7月の予定
2019年7月の予定
今年は梅雨らしい梅雨、というか例年に比べてかなり本格的に
雨が降り、1日としてカラッと晴れた日が続かない感じですね。
人は意識していなくても体は天地の影響を受けていることが多く、
実際むくみやすかったり、重だるい、疲れやすい、頭痛、めまいがする
という方も多いのではないかと思います。
自然界の『水』が増え、さらに毛穴も湿気に塞がれ汗をかきにくい状態。
日々の習慣で冷たいものを飲食したりしていると上記のような症状は悪化
しやすく、夏が来る前から夏バテのようなことになりかねません。
また、一日として、安定した天気の日が続かないので
日々天候のアップダウンが体だけでなくメンタル(自律神経)にも作用し、
イライラしやすかったり、鬱々しやすかったり、気だるさなどから
どうにもすっきりしないような日が続くようになってしまいます。
適度に運動をして汗をかいたり、冷たいものを飲食しないといった、
基本的なことを外さない、ということが大切ではないかと思います。
参考:梅雨の養生と胃腸のケア
7月の予定
・定休日:毎週水曜日(3・10・17・24・31)
・不定休日:11・13・25
・午後休み:4・18・28
☆各種講座
・3日:ノキロアートネットさん/お醤油豆講座
・15日:白馬気功
・24日:上田アリオさん/妊活養生講座

2019/06/19
梅雨の養生と胃腸のケア
梅雨の養生と胃腸のケア
東洋医学では一年を四季だけでなく
その季節と季節の変わり目、梅雨の時期を五行の
『土』の時期と捉えます。
土、そのものは湿り気があり、養分を蓄え万物を成長させる土台。
人の体の中で五臓は『脾(ひ)』という働きが
成長の中心となる栄養・水を吸収し、気・血を作り
全身の水の流れを統率し体を支えていく土台となります。
この『脾』というのは東洋医学独特の臓腑、いわばシステム・働きであって
実像があるわけではないので西洋医学的な『臓器』を当てはめにくいのですが
働きとしては『腸』の吸収システムに当たると考えることができます。
つなり、東洋医学でいう『脾』という消化吸収の働きは消化の働きは『胃』と
吸収は『腸』によるもの、ということになります。
腸は東洋医学でも『小腸』・『大腸』は六腑に属しますが、
特に『栄養の吸収』という観点から見たときには五臓の『脾』が相当すると
考えることができます。
命を繋いでいくために必要な栄養を吸収し、それをエネルギー(気)や
栄養を含んだ水(血)を作り出す場となるのは『脾であり腸である』ということ
になります。
胃が弱いのか腸が弱いのか
「胃腸が弱くて・・・」という仰る方がいますが、詳しくは
胃が弱いのか、腸が弱いのかでは消化が弱いのか、吸収が弱いのか
という違いになってきます。
『胃』というのは食べたものを分解し、吸収しやすい状態にする場なので
胃が弱い、胃もたれを起こしやすいという方は消化しやすいものを
召し上がる、ということを心がけるようにします。
一方、腸が弱い、というのは吸収しにくい、つまり
栄養を受け取りにくい状態で気血を作り出しにくい状況になってしまいます。
また、腸では食べたものからの栄養を吸収しるだけでなく水も吸収しています。
しかし、腸は水っぽい状況が苦手です。
適度に湿っていないと便秘になってしまいますが、水が増えてしまうと
下痢をしてしまう。
大地のシステムと一緒です。地面が乾いてしまっては作物は芽を出してくれませんし、
水が溢れてしまっては根こそぎ流れてしまったり、腐ったりしてしまう。
腸の働きは『水』の量に影響されやすい、と言うことができます。
その『水』と言うのは体の中でたまると、たまった場所で気血の巡りが
悪くなり、また、冷えやすくなります。
腸にたまってしまうと腸が冷えてしまい、
下痢が一向に治らないと言うことになります。特に梅雨の時期や『土』
の時期というのは自然界の水が増え、脾の働きが弱くなりやすいため
体の中の水の流れ、排泄を促すようにしながら、脾の働きを
整えておく、ということが大切になります。
体の中にたまる水は病理産物を作りやすい
『水』が体の中で溜まったとき俗に言う『水滞』と言う方も
いますが、『痰飲(タンイン)』とも言います。
(このブログでは痰飲で書いていきます。)
痰飲は浮腫み、と言う初期の段階では食べ物や汗をかく、などで
比較的、改善しやすい状態です。が、それを放置しておくと
だんだん溜まっていた水が粘着してきて、流れが悪くなります。
スライムのような状態ですね。下半身ではセルライド、と言う
脂肪の塊のようなものができ、また静脈瘤などの瘀血が
生じているような浮腫んだ足、と言うのをイメージしていただくと
わかりやすいかと思います。
下半身のセルライドや静脈瘤は体の表面なのでわかりやすいですが
実際は内臓を含めて全身のいたるところに痰飲は生じます。
頭部にも生じてくると水が溜まったようなボワーンとした
耳鳴りや、鼻づまり、めまい、頭重感などが生じたりします。
また、その症状は天気が悪くなる前になると悪化する傾向があります。
また、胸、卵巣、などにも溜まるとやはり厄介な病理産物を
作り出してしまったり、関節にたまると関節の痛みやしびれなど
が生じてきます。腸に貯まれば下痢になり、胃に貯まれば吐き気・胃もたれ
につながる、と様々な体調不良の原因になりやすいのが水の滞りである
『痰飲』となります。
それだけでなく、痰飲はもともと『水』ですからタルミが出てきます。
浮腫みなのかタルミなのかわからない・・・と言うことが
生じてきます。これは体型だけでなく、顔のたるみにも
当てはまることですから高価な美容液を使うよりも
痰飲を作らない、と言うことを心がけたほうが美容にも
良い影響が出てきます。
胃腸が元気な方は肌艶良く、ハリもある、と言うことですね。
脾を元気にして『痰飲』を作り出さない
『脾』の調子が良いと食べたものからの栄養の吸収が良くなり
体にも余計な水が溜まりにくく、スッキリした状態になります。
浮腫みも生じにくく、お通じも快調、と言う理想的な状態です。
そして上記にもあるように、見た目にも肌ツヤが良かったり
張りがある。体も余計なタルミがないわけです。
どうしたらこの状態になるのか?
腸を冷やさない、生ものを食べない、食べ過ぎない、
油・甘味を控える、です。
シンプルです。
特に最も避けなければならないのは
『冷たい+油+甘い』の組み合わせ。
これは体に一番溜まりやすく、いろいろな病気の元となりやすい。
甘味といっても甘味料の甘味や果物の甘味になります。
穀物、特にコメなどの甘味は生活していく上でのエネルギー源としては
必要なものです。
穀類・芋類などの炭水化物はエネルギーとして必要なものですが
肉体を作り、肉体を維持していくために必要なものはタンパク質です。
嗜好品としての甘味をできるだけ減らす。
どうしてもの時は『冷たい+油』が加わらないようなものを食べると言うことです。
そして、腸の中の細菌が喜びそうな餌、食物繊維などを含んだ食材や
発酵食などを増やしてあげると腸そのものも元気になってきます。
梅雨の時期は脾の働きが低下しやすく、体の中に
痰飲ができやすい時期です。夏が来る前に胃や腸の働きを
整えて夏の暑さに負けないように整えておく大切な時期です☆
8月のカネマツ講座でも引き続きこの脾について説明しますので
ご興味のある方は是非ご参加ください。

今月のカネマツさんのお弁当は食べ応えがありました〜!!
・タケノコと梅かつおのご飯
・ひじきのマリネ(レモンの香りがとっても爽やか)
・巡りチャプチェ(紫蘇や山椒を少し加えて)
・さっぱり夏の黒酢煮(黒酢は血の巡りを改善してくれるます)
・じゃがいもともずくの味噌汁(1日1種類は海藻を食べることをお勧めします)
・長芋のおやき・梅味噌(もちもちこんがり。美味しいおやつ!)
参考記事:
・めまいについて
・デトックスと東洋医学
2019/06/11
色々な発熱・熱証
色々な熱証
東洋医学では体の中にできる熱・寒でその時の
エネルギーの状態をみます。
単純に熱証は『体が熱っぽい』という状態を指すわけではありません。
身体の熱と精神の熱
『熱』は身体だけでなく、精神にも生じます。
『身体的な熱』は元々エネルギーの状態が強いタイプの方です。
やはり、見た目にもエネルギッシュだったり、疲れ知らず、という方に多いです。
一方、『精神の熱』というのが東洋医学ならではの視点です。
精神の熱が
・良い動きをしている時=エネルギーが充実している
やる気がみなぎる、エネルギッシュ
・動きが良い状態ではない時(気滞)=エネルギーが溜まってる
ストレスが溜まって発散できていない・イライラする・眠れない
という大まかな表現になります。
ストレスが溜まりやすい、緊張しやすい、という方はエネルギーの流れが
滞りやすい『気滞(きたい)』という状態になりやいです。
気持ちの面で熱=エネルギーが充実していてそれをうまく使えている時と
そうではなく、エネルギーが溜まっている状態になってしまうときがあります。
溜まっているエネルギーを発散しようとお酒を飲んだり、食べ物で発散したり
運動で発散したり、と無意識の中で『発散』させようとしています。
ただし、お酒を飲んだり、食べ物(辛いもの・甘いもの)で発散させようとすると、
さらに熱を溜めてしまうことがあります。
元々の性格的なこともありますが、溜め込んでしまう、という方もいます。
その場合、その溜まったエネルギーが人によっては
・発熱・下痢・出血・湿疹(アトピー)
という熱を身体の外へ出そうという身体表現が体調変化として現れることがあります。
元々の身体的にもエネルギーが比較的強い方は発熱(高熱)・出血(特に鼻血)、と言った形を
とることが多いですが、そうでない場合は下痢や湿疹という形をとることがあります。
また、便秘などをしているとやはり排泄での熱の発散ができなくなるので
熱がたまりやすくなります。
わかりやすい例で言えば、便秘をすると吹き出物がでる、と言った感じですね。
(夏は特に便秘しやすく、熱がこもりやすくなりますから
肌荒れが気になる方は辛いものを食べるのは控えた方が賢明です。)
基本的には『熱』というものを発散させるときは体を動かして汗をかいた方が良い、
と考えています。
ためすぎて体調変化として出ないようにした方がいいわけです。
汗を書く、と言っても大汗かくようなほどではなく
汗ばんだな、という程度位とどめておいたほうが身体のエネルギーを
消耗しすぎることがなく、運動して疲れる、ということは防げます。
特に女性は汗をかきすぎると『血』の消耗に繋がってしまい
血の巡りが悪くなってしまうことがるので要注意です。
汗をかく、というのは熱の発散になり、
夏でも汗をかけないと熱がこもりやすくなってしまいます。
子供でも熱中症などで痙攣などを起こしてしまうことがあります。
日頃からよく遊ばせて汗をかきやすい状態にしておいてあげることが
大切です。
また、大人でも冷房が効いた中にずっといると下半身が冷え切ってしまい
熱が頭部にたまりやすくなります。汗をかいているからと言って
氷の入ったものを飲んだり、冷たいもの、生物を食べたりしていると
熱がこもりやすくなってしまいます。
夜は足湯をしてしっかり下半身を温め、頭部はアイスノンなどで冷やすようにする
のがオススメです。
夏は夏野菜で熱を冷ます
食べ物では熱を発散させる辛味のものがありますが、前述したように
熱がかえってこもってしまうこともあります。
辛味のものを食べて水分をがぶ飲みして胃腸を働きを弱めてしまいかねません。
また、辛味のものは一時的にエネルギーが上昇するので
スッキリして、元気になったような気がしますが
そのあとにドッと疲れる元になったり、イライラの元になりやすいので
要注意です。
キャンプなどで焼肉、ビールなどで楽しくやった後に
ドッと疲れたり、夜に眠れなくなった、なんて経験ありませんか?
夏はトマトやキュウリ、ゴーヤ、などの夏野菜や海藻などを食べて
日頃から熱が体にこもらないようにしておきます。
ただし、生で食したりすると胃腸を冷やしすぎて
しまうことがあるので、サラダや味噌きゅうりで食べるよりも
お酢・生姜やミョウガ、シソなどを組み合わせてマリネのように
して食べた方が、夏バテの予防にもなります。
また、健康志向で玄米を食べるのも夏は控えめにして
せめて5分づき米に押し麦などを加えるなどするくらいにして
熱が便や尿などの排泄物で発散できるようにしておくと、
『精神の熱』がこもらず、夏でもあまりイライラしたり、眠れない、などということを
防げるでしょう。
2019/06/07
養生は健康貯金
『養生』とは
なつめやはお客様の体調や体質などを伺って
そこに季節などを考慮して漢方薬をお作りしています。
カウンセリングでは食事の内容や就眠時間など
生活面も必ずお伺いします。
漢方薬は体質改善や体調を改善するためのものですが、
ご自身の食事や生活習慣などを見直さなければ
改善できるものもできないことが多いからです。
例えば病院でコレステロールが高いから、血糖値が高いから
と薬をいただいても、相変わらずの油っぽい食事や
甘いものなどを食べていては改善しないのは想像に難くないことです。
しかし、運動は?というとそれはできる方もいればできない方もいる。
食事の改善も運動も同じくらい大切なことです。
それは漢方薬も西洋薬も同じことです。
ですが、東洋医学はその人の『気』というものも観察しますので、
『気』が不足せず、滞らず、ということも重要視します。
『気』というのはエネルギーですから疲れていれば休む、
ストレスなどで滞っていればストレスをうまく流す、
そして、過剰な刺激を与えない、ということも意識します。
様々な刺激は心を活発させることもあれば
疲労させることもあります。
運動も適度なものは身体をほぐしてくれますが、
健康に良いからと激しすぎる運動はむしろ身体を疲労させ、
精神的には交感神経が優位になってしまい興奮しやすくなってしまいます。
体が疲労して頭が興奮しているなんて、あまり健康的ではないですよね。
心身が程よくほぐれる、ということが大切。
ストレスを発散するためにお酒を飲む、甘いものを食べる
など、意識的にしている場合も、無意識にしていることも
ありますが、どちらも心身にとっては不健康な状態です。
ストレスのため、と意識できていればまだいいかもしれません。
『養生は健康貯金』
『養生』というのは食事や生活習慣だけでなく気持ちの面でも
ストレスを溜めず、生命力を高める習慣の総称です。
そして、私は『養生は健康貯金』だとも考えています。
日々、歳をとります。
それは生まれてから以降は成長し、成熟し、ある一定の成熟の頂点を
迎えると誰しも生命力は緩やかに下降していきます。
そしてやがて死を迎えます。
『養生』というものは『生(せい)』を『養う』と書きます。
自分の命のエネルギーを高めるもの。
死に向かってきていく中で、より自分の命を輝かせ
生活を充実させ、様々な活動を味わい尽くすために
『命のエネルギー貯金』としてコツコツ積み立てるものと
考えてみると、少し、養生に対しての考えが変わりませんか?
あれもダメこれもダメ、あれやれこれしろ、はヤダヤダ
と思うかもしれませんが、自分のための
『健康貯金』としてコツコツ積み立てるのは、案外楽しいかもしれない。
一日の終わりに自分の命のエネルギーはどのくらい消費し
朝起きた時にしっかりチャージできているのか?ということを
意識しないでいると、常に消費しつづけ
心身は消耗の度合いが強くなっていきます。
生命力の緩やかな下降が急降下することもあり得ます。
自分が自分のためにできることが良い習慣であれば
心身は良い方へと反応します。全く病気にならないとは
言い切れませんが、早い段階で気付いたり、見直すことで
改善も早くなります。
悪い習慣を続けていれば心身に『病』というものが
生じやすい状態になり、なかなか改善しにくい状況が生じます。
身体にとって良いことが心にとっても良い方へ作用するかといえば
初めは食べ物などは制限することもあるとストレスに感じるかもしれませんが
慣れてくると食べ物の内容や、味付け、嗜好も変化してきます。
濃い味付けや刺激物は食べるほどにより強い刺激を求めるように
なっていきます。
過度な刺激は興奮的なものが多いかもしれませんが、
リラックスするような穏やかな時間も楽しむことができれば
むしろその方が、命のエネルギーにとっては余裕が生まれてきます。
1日の終わりに自分のパワータンクが10のうちどのくらい減っていて
1日でどのくらいプラスになることができたか、マイナスになることを
したか、少し見直してみると良いかもしれません。
そして、朝起きた時に自分の体がしっかり回復してパワータンクが
10よりも超えて充電できていれば『養生貯金』が少しできている。
そんな養生生活を出来るだけ多くの方が経験していただけたらと
思います。なつめや はそういった養生をその方に合わせた提案をしたり、
また毎日のメルマガでヒントとなるようお伝えしています。
一人でも多くの方が心身健康で、そして、その心地よいエネルギーが
拡がっていくことを願ってやみません。

2019/06/02
なつめや2019年6月の予定
なつめや 2019年6月の予定
そろそろ梅雨入りの時期になりました。5月は異常な暑さが一時あり、気温差が大きく
また、GWの疲れなどもあり、身体が疲れを溜めている方も多いようです。
『疲れた』と言うことを実感できる、と言うことが大切なことです。
常に外向きな、いわゆるやる気満々な方々は『疲れ?なにそれ』くらいに
感じるかもしれませんが、やりすぎた後にドッと疲れが出たり、
風邪をひいたり、など体調の変化が出てきます。
夏は特にそう言う傾向が強くなります。
太陽の光は明るく、日も長いため人間もその影響を受けて
活発になりやすく、その反面、睡眠時間が短くなり、
疲れを感じないまま溜めてしまいやすい時期になります。
さらに急に暑くなったために、冷たいものを飲食しやすくなっていますが、
内臓を冷やしてしまい、食欲低下、重だるい、めまい、頭痛、吐き気などの
体調変化が出てきている方もちらほら。
頭部をアイスノンなどで冷やしてあげることで脳の熱が下がり、
『暑い』という感覚を和らげることができます。
暑いさなか、温かいものを飲食すると言うことは難しいですが、
せめて常温のものにしたり、冷たいもの・生物・アイスなどは控えるように
心がけることをお勧めします。
夜に窓を開け放しにしたり、これからエアコンを入れて身体が冷え切ってしまう
こともあるので、朝の1杯の白湯もお勧めです。
『養生』と言うのはこうして書いていると、非常に意識が静かな方へと
変化していくので、強い刺激や嗜好というものが減ってきます。
多くの人は強い刺激や嗜好、本能的なものを好み、『養生』というものに
ある種の物足りなさを感じるかもしれません。
要は『メリハリ』
好きなこと、楽しみにしていること、自分が大切にしていることなどを
やる、ということを心から充実した状態で成し得て、
そのあとの心地よい疲労感や、豊かさを実現するために
心身が健康である、ということ。
このために『養生』があって、それは『静と動』であるかのようです。
常に『動』だけでも、『静』だけでもなく、それぞれを
意識して生活していくと、自然とどちらも自分の身となるのではないかと
考えています。
そうした中で、楽しみが増え、深みもグッと増して、様々なことを
楽しみきれる。
疲れた体と心を奮い立たせて、あれもしなくちゃ、
気が乗らないけれどお付き合いしなくちゃ、では
楽しみきることなんてできなじゃないですか。
好きなもの、冷たいもの、アルコール、甘いものなど好き放題食べて
その先にはなにがあるでしょうか。
最終的にはそれらを制限する時がやってきます。
本当に美味しいな〜、と思うお酒を飲んだり、
少しの甘いおやつは至福のものになるように、とっておきとして
あるからこそ美味しいのです。
できるだけ心地よい体と気持ちで日々の生活を営む、
そのための『養生』と考えています。
夏の過ごし方は1年のうち最も過ごし方が難しい時期と感じています。
疲れを溜め込まないようにお過ごしくださいませ。
6月の予定
☆カネマツ薬膳講座:6月19日(水)☆お休み
・毎週水曜日
・臨時休業:8・13・20・27日
・午後休み:6日
2019/05/29
妊娠はゴールではなくスタート
妊娠はゴールではなくスタート
『妊活』をしている方々、そして、これから始めようと考えている方に妊娠はゴールではなく、新たなスタートの第一歩にしかすぎないよ、
ということをお話します。
妊娠前の体づくりがいかに大切か
妊活を目的に初めは病院へ行って検査や治療を受ける女性が多いかと
思います。そして、それが功を奏することができず、東洋医学の
漢方や鍼灸で体を整えよう、とお考えでご相談にいらしゃっています。
また、結婚前から体調を整えておきたいとか、病院ではあまり
積極的な治療をする気になれない、という方もいらっしゃいます。
東洋医学で体を整える、ということが『妊活』において
その人の体だけでなくその後の生活にも影響していくことがあります。
というのも、妊娠したらその後、10ヶ月赤ちゃんをお腹の中で
育て守りきる、まずその体力、体づくりとなります。
妊娠したら全員出産できればそれはとても喜ばしいことですが、
現実は難しい局面が妊娠後何回か訪れることもあります。
心拍が確認できるまで、安定期に入るまで、つわりとの戦い、
逆子の心配、早産・流産の不安、幾つもの困難が訪れることがあります。
それを、乗り越えていく体にしていく、ということです。
また、妊娠中の過ごし方、栄養条件などはお腹のお子さんにも
影響が及びます。そういったことを学ぶ機会が妊娠前に『妊活』
ということで自分の体を通じて食べ物や生活習慣、子供の成長について
学ぶ大切な時間になります。
そしていざ出産となった時でも、すべての人が安産とも限らず
やはり出産時のトラブルもあり、産後の体調不良や
更年期などに影響が出てくるケースがあります。
また、最近では第2子がなかなか授からなくて・・・という声もあります。
特に最近は産後のトラブルが更年期時期に現れてくるという
ケースも多いなと感じています。
妊娠前からの準備が出産、産後、第二子、更年期へとつながっていきます。
その中で『妊娠』というのは結婚を機にした
第2の人生のファーストステップなんだと思います。
決してゴールではないですね。
妊娠まではエネルギーが登り基調であるのに対して、
妊娠後の方がはるかに長く、出産から子育てという
大きな力を必要とし、体も充実した時期から更年期へと
性の力が落ちていく時期も含んでいるからです。
そして、育児をしていく中で妊娠前に学んだことが
子供の食・生活習慣に母として自然と反映させていくことが
できたとしたら、それはその子が生きていく中で
また次の世代へつながっていく力になり得るのではないかと考えています。
東洋医学では『母病及子』という言葉があり
母親の病は子に及ぶ、というものですが、それは
病だけでなく、良い習慣、食事なども子供に影響する
とも考えてることができるのではないでしょうか。
『妊活』は単なる子作りのため、というよりも
これからの家族のために必要な学びの時間であり、
焦らず、しっかり土台を作るような気持ちで
臨んでいただければと思います。
漢方薬がその手助けになり、ご自身の力を
引き上げていくもの。
そして、その中で学ぶことも目には見えませんが
大きな力になっていきます。
妊活薬膳講座は
上田アリオのヒルトップカルチャー さんでスタートしました。
途中からの参加も可能ですので、ご興味のある方は
ぜひご参加ください。
また、妊活に限らず、全般的な薬膳・養生講座は
偶数月の第3水曜日に松代カネマツ倶楽部さんで
開催しております。
☆なつめや 講座情報
2019/05/01
令和元年5月の予定
令和元年5月の予定
新たな元号となり、新しい時代が始まりました。平成の戦争のない平和な時代で様々なことが便利になり
これからどのように発展していくのか未知の領域ですね。
平和を自らの心の中で実感できるようでありたい、と
常々思っています。
一つ、これからの流れとしては医療は『遺伝子』という分野で
大きな変化を遂げ、それは自分たちの健康や食べ物
生きていく土台に深く関わり、ますます『自分の意志』というものを
が大切な時代になるだろうな、と感じています。
食べ物も栄養的に、そして栽培的に都合の良いように遺伝子が
変化したものが登場してくるかと思います。
もちろんそれはそれで、農家さんたちの手間も省け
より多くの作物を作ることもできるでしょうし、栄養的に
特化したものを食べることが栄養学的には好ましいことかもしれません。
また、そういうものではなく、オリジナルの原種に近いものを
食べたい、と思う流れもあるかと思います。
食のこだわりも強い人もいれば
食べれればなんでもいい、という考えの人もいる。
どちらも有りで、何を選ぶかは自分の意志によるところです。
食べ物は栄養素でできているわけではないし、私たちの体もパーツで
できているわけではなく、そこには生命として存在するエネルギーが
ある、ということを頭の片隅に入れて、何かを決める時の基準の何かに
引っかかってくれればいいかな、と思います。
物質的な考え方とエネルギー的な考え方が分離せずに
一体となって人生を支える。
それこそが陰陽の統合ではないかな、とお思います。
人生を輝かせる、というのは誰かに輝かせてもらうのではなく
自分で輝かせることから始まり、
それが家族の光になって、周囲の人への光として拡がっていく、
と私は考えています。
自分自身がまずどうなりたいのか?を意識していくと
食べ物、体、環境、いろいろなことが今までと
少し違う視点で見えるようになってくるかもしれません。
そういった時に、なつめやの講座やカウンセリング、ハーブティー・漢方が
何かのお役に立てれば幸いです。
5月の予定
・1〜6日までGW休み・15・22・29(水)定休日/8日は臨時開店日
・10日・18日・30日臨時休業
・16・23日半日午後休み
5月の講座
・上田アリオ『妊活薬膳講座』早朝のお朔日参り、清々しくてオススメですよ。
2019/04/17
今年も始まりました『カネマツ薬膳講座』
今年も始まりました『カネマツ薬膳講座』
2019年も松代のカネマツクラブ倶楽部さんで薬膳講座を
させていただくことになり8年目に突入です。
毎年、開催させていただき色々な方が学んで、家庭のご飯に
生かしていただいて、少しずつ食や健康に関する意識の良い変化が
拡がっていって、ありがたいことです。
今年の私の中でのテーマは
『食べ物と自分の体、自然のエネルギーの調和』になります。
薬膳というと、陰陽五行や気・血・水を基にして体の変化や食べ物などを
変化させていく、というのが基本になります。
ただ、私としてはもっと食べ物のエネルギーや自然のエネルギーを
感じて、理論や理屈だけではなく自分で感じ取る力、五感の力を
つかてそれを薬膳に生かして、より自然に調和していけるように
1年を通じて講座の内容を考えていく予定にしております。
薬膳の基本は『食べ物からのエネルギー』をいただくということ
例えば春は苦味でデトックスして五臓の肝の気を流しましょう、
としたとしても、そもそも肝の気、もっというなら体の気を
が自分が納得して感じれていないと流れているとか
滞っているとかよくわからない。
流れている状態もよくわからない。
気(エネルギー)は目に見えないですし、そもそも
エネルギーについてよく考えたこともないかもしれません。
よくわからないところで、いろんな情報に振り回されるよりも
自分の感覚で滞っているな、とかめぐりが悪いな、とか
感じてそれに対応した食事や活動をしたら良いですよね。
そのために知識の土台として東洋医学の
陰陽五行や気血水があります。
土台がしっかりして、感じる力があれば無敵(笑)
応用は自分ですれば良いことです。
陰陽五行から自然と食べ物・人のつながりが見えてくる
陰陽五行や気血水の理論から体と自然・食べ物のつながりが見えてきます。
ただ、食べ物を栄養学的に見るのと『薬膳』という名の下で
この食べ物はこの季節で、こういう働きがあってというのは
大差ないような気もしています。
土台の自然・食べ物・自分のエネルギー(気)を感じ取ってこそ
野菜の働きなどを取り入れた薬膳ができるのではないかと考えています。
春、と言っても日々天気がコロコロ変わる中で
春の薬膳は〜と理屈でやるよりも、その日の感覚や体の調子を
中心に考えた食事で体調を整える。
この食材は例えば血がサラサラになる、とメディアでやっていたとしても
夏と冬では血の滞りかたが違うし、人によっても違う。
やはり基本はその人、季節に合わせる、ということだと。
食物の気を感じてみる
同じ大根でも産地や作っている人によって味も違えば
美味しいと感じるのも違う。
それと同じように食事を作る人が違えば、例え調味料や条件を
同じにしたとしても食べたときの感覚や味は
異なることがあります。
そこに生じる『気・エネルギー』の違いや
作る側のエネルギーの状態によっても違いが生じてくるような。
そこで本日は実験で
普通に炊いたご飯と、そのご飯に『美味しくな〜れ』と
気持ちを込めて握ったご飯を食べ比べるということをしてみました。
作る人のエネルギーで同じご飯でも食べたとき
どう感じるのか?を比べてみようと。
皆さんに感想を聞いてみるとはっきりした味の違いというよりも
口に入れやすい、食べやすい感じがする、ということを
おっしゃっていました。
なんとなく自分の口に馴染みやすい味のような。
というのは自分のエネルギーと食べ物のエネルギーが調和して
食べやすく、体に取り入れやすくなったのだと考えることができます。
色々なエネルギーを感じることできるようになると
今まであまり好まなかったようなものを食べれるようになったり
食べていたものが急に美味しくないと感じたりと味覚に変化が
出てくることもあるかもしれません。
自分の体をしっかり感じると味覚まで変わる(笑)
そうした中で、本当に食べたいものや美味しいなと感じるものが
体にとって栄養となり、気(エネルギー)・血・水となって
肉体を作り命の営みを継続していく原動力になっていく。
欲望(笑)で食べていて、本来不要かもしれないものを食べていて
病気になってしまうかもしれない、予防につながりますね。
本当に必要なもの、美味しいと感じるものを
季節や食べ物・自分の体のエネルギーを調和させて
心身が健康になるような実験を交えながらの薬膳講座。
ご興味がりましたらどうぞご参加ください。
本日のお弁当の内容は
・新じゃがとスナップエンドウの春いろソテー
・キャベツとアスパラの春巻き
・独活と菜の花の香り白和え
・めかぶと長芋のトロトロご飯
・かぶのみぞれ味噌汁
・よもぎの豆腐白玉

なつめやブログblog
month's schedule今月の予定
month's course今月の講座

 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ スケジュール
スケジュール
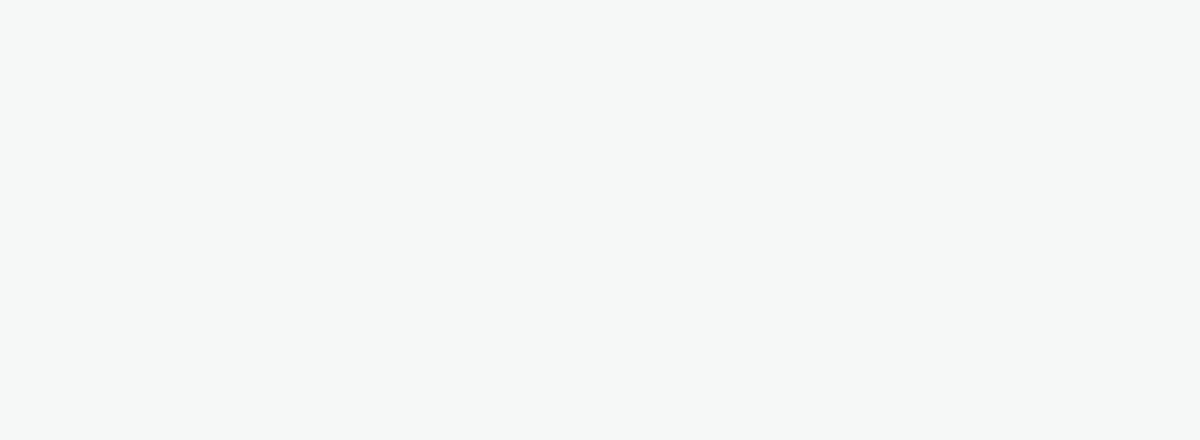


 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ Skypeでのご相談
Skypeでのご相談 スケジュール
スケジュール

