2019/01/04
謹賀新年2019
謹賀新年 2019
新年あけましておめでとうございますなつめやは1月5日より新たな年の営業をスタートします。
なつめや に来てくださるお客様にはより健康になって
『体も心も気持ちがいいな〜』と実感していただけるよう
精進し、一層気を引き締めて、伴走させていただきます☆
そして、今年は自分のエネルギー(気)を感じていただけるような
フィールドワークも本腰を入れていく予定です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

☆☆1月の予定☆☆
水曜日定休日:9・16・23・30その他のお休み日:14・18・19・24・31
カネマツ薬膳講座:16日
初詣で戸隠の奥社へ。
山の気がぴりっと清浄な感じでした。
今年は山でいい気を感じ、瞑想をする
合宿をやっていく予定です☆
2018/12/28
一年ありがとうございました
一年ありがとうございました
本日、なつめやの2018年の営業を終えました。ご来店くださった皆様、そして、講座やワークショップに
参加してくださった皆様ありがとうございました。
たくさんの方とご縁をいただき、いろんな意味で多くのことを
学ばせていただきました。
今年一年、『エネルギー』や『気』について意識しながら
体のこと、心のことを伺ってきました。
人の体に流れているものは血だけではありません。
血が流れているのは心臓が動いているから、だけではないです。
心臓を動かす力、血管が動く力、があって血は流れています。
原動力となっているのが『気』です。
実際に目に見えるものが動く、というのが当たり前のように
思えるかもしれませんが、人とモノの大きな違いは
『エネルギー』の違いです。
生きるものすべてに備わっているエネルギーですが、
目には見えないので、その存在を意識しにくく、
自分のエネルギーがどんな状態か?ということも
わかりにくいです。無茶をして体調を崩したり、
ストレスによってエネルギーの流れに滞りが
生じていたり、ということをどうしたら、意識できるように
なるのだろう、とずっと考えてきて
気功の講座をさせていただいたりしていました。
一つの結論は『考えるよりも、実際に動いて感じる』こと。
そして、『感じる』ことができる『余裕』が必要かな、と思います。
仕事や家事や、趣味でスケジュールをいっぱいにするのではなく
少し余裕の時間を持たせ、生活のペースを少し緩めるだけで
いろんなことが見えたり、聞こえたり、感じたりすることが
できるようになります。
例えばゆったりしたカフェにいると音楽が聞こえ、コーヒーの良い香りや
甘いお菓子の匂い。そこにある空間の居心地の良さ。
いろんな感覚が刺激され、とても満ち足りた時間を過ごすことができますよね。
自分の体についても同じように、少しゆっくり体を動かし
呼吸や自分の体の動きを観察していくと
自分の中にある、動きの中の気持ちの良い流れを感じることが
できる時があります。
それを実感できた時、日常の緊張した時などの体がこわばる感覚や
疲れている時の体の鈍さ、重さを感じやすくなるかと思います。
体の違和感が積み重なり病気の入り口に入っていくことに
気づくことができるようになるかもしれません。
それは自分の体を守る第一歩のように思います。
来年以降、医療は大きく変化していくと感じます。
AIによる診療や外国人医師などが入ってくることも考えた時、
自分、家族の体を守っていくのは自分たちの意識に他ならないと思っています。
実際にワークショップなどに参加してくださる方々を見ていて
自分の体の状態を自分が少しずつでも感じれるようになり、
自分の体が見た目にも、エネルギー的にも変化していくと
人はこういう表情になるんだなぁというのを目の当たりにします。
人はこんなふうに変われるんだなぁと。
来年もこの流れをさらに拡げて活動していきますので
どうぞ皆様ご参加くださり、自分が変わったな〜という
実感を感じてくださいね☆
なつめやは1月4日までお休みをいただきます。

2018年、感謝を込めて。
なつめや 柏崎美恵
2018/12/21
黒豆味噌造りの全行程
黒豆味噌造りダイジェスト
12月19〜21日に糀造りからの黒豆味噌作りを行いました。
昨年までは松代のお寺の境内で、お寺の大きな鉄鍋で
助っ人を頼んで黒豆を煮て、買ってきた糀で味噌を仕込んでいました。
糀造りからを全て経験するというのは初めてです。
1日目:糀づくり
前日に洗っておいたうるち米を蒸します。
気持ち硬めと柔らかめの2パターンの炊き上がり。
麹菌は成田屋さんから原種の麹菌を分けていただきました。
薄い緑色の麹菌を炊き上がったうるち米を冷ましてからふりかけ
混ぜます。この時、少量の米に麹菌を混ぜた濃度の濃いものを全体の米に
投入するという方法にしました。うっすら色がついたかな、というくらいなので
糀が満遍なく行き渡っているのか心配しつつも、保温機へ入れて
発酵させ始めました。温度は35度前後。

2日目:糀の手入れ/黒豆を煮る
発酵器から糀を出して空気を入れるように糀をほぐします。
大した作業ではないですが、糀菌がついていて一安心。
さっさとやって保温器へ入れます。
今日のメインは黒豆を煮ること。
一昨日から水に浸しておいた黒豆を寸胴鍋で煮ます。
出来上がり100キロに対して前年よりも若干少なめの
22キロの豆を煮ます。
寸胴で煮ること2時間経つ頃に助っ人がきてくださり、
煮えかたを確認してもらうが、まだまだ、ということで
のんびり煮ます。
その間にパパッとおいしいおかずを作ってくださったり、皆さん
あれやこれやと色々と美味しいものを出してくれました
(自分は何も持ってこなかったことを悔やむ・・・・。)
途中でびっくり水を2回ほど入れてみました。
こうすると豆の皮と身が離れず、中の身までしっかり熱が入り
柔らかくなるのだそう。

3時間くらい経った頃、いい感じの柔らかさに煮上がる。
目安は親指と小指で豆が潰れるくらい。
食べた時に豆の皮の感触がほとんどなく、口の中ですぐに
潰れる感じがします。
このくらい柔らかくしておく、ということを忘れないようにしよう。
いつも人任せだったので良い勉強になりました。
3日目:いよいよ味噌造り
黒豆を少し温める、つもりがしっかり火入れをしてしまう。
しっかり火入れしなくても、少し温かいくらいでいいのに、
あれやこれやと段取りを話していたら豆が温まり過ぎた(笑)
糀を発酵器から取り出し、塩をまぶす。
ほんわか温かい糀。

豆を潰す機械でガンガン潰す。
夏に仕込んだときは皮が機械に目詰まりして大変だったのが
嘘みたいに快調に潰せる。
豆の煮方・柔らかさがこういうところで違いを生むんだなぁと
改めて気づく。
豆が温かすぎるのでうちわで扇いで冷ましてから
糀へ投入。混ぜる、混ぜる、混ぜる。
なんせ100キロ分なので作業台が小さく
作業しにくいのを皆さんの知恵を絞り
うまいことやっていただきました。

出来上がりは黒豆が若干少なめだったのにも関わらず、101キロの出来上がり!!
初めて自分たちで全行程をやりきり、上出来の仕上がり。
最低半年は寝かせますが、出来上がりが楽しみですね〜!
ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました!
2018/12/19
食の大切さ、と薬膳
食の大切さ、と薬膳
なつめやは薬膳を通じて『食の大切さ』をお伝えしています。
『食の大切さ』というのも色んな解釈ができると思います。
私たちの体はまさに食べたものから作られ、動いて
成長し、子孫を残し、そしてやがて死に向かっていきます。
『食べ物』が私たちを支えているので『大切である』というのは
認識しやすいかと思います。
『食の大切さ』って具体的にどんなことなの?
素材はオーガニック、無農薬とか
時間をかけて丁寧にとか
こういう効能があるからこういう時にはこれを食べる、とか
そういったことが中心になりやすいですね。
薬膳は特にそれぞれの食べ物の効能というか、特徴をつかんで
自分の体質や症状に合わせて食べる、ということを
学んでいきますので、その部分を意識しやすくなります。
確かにその点は知っていると体にとっては良い変化が出てきやすくなりますので
知っているのと知らないでいるのとでは、それぞれの食材の特徴を
知らない、というのは少し損だなぁとおもうことがあります。
どうせ食べるなら、どういう風にいいのか?ということを知っていると
食べる時にも自然とそういう意識になりますし、
食べた後、なんとなく満足感が高くなるようにも思います。
私は、こういう食べ物よりはこっちの方がいいかもね、という
話し方をします。これはダメ、あれはダメ、っていうのはしんどい。
植物性と動物性の区別もしません。オーガニックや無農薬ができれば
いいかなと思いますが、それだって人それぞれのお財布事情や
価値観なのでこれじゃ無いとダメ、とは思っていません。
自分が何を選ぶか?だけなのだと思います。
スーパーへ行って『あ〜、これ美味しそう!!』って選んでいるか?
あまり、よく見ないで日付だけ確認して選んでいないか?
ということを含めて、自分がしっかり素材を見て選ぶ。
それって、食べ物のエネルギーを選んでいる、っていうことの
出発点だとおもうのです。
そして、その選んだ食材を
自分の体を作ってエネルギーになってくれるよう
活かしきるための薬膳なのではないかと思っています。
素材のエネルギーをしっかり発揮できるように
自分が調理していく中で、自分のエネルギーも
料理には入っていきます。
嫌々やっていては嫌々エネルギーが入ってしまう(笑)
自分だけでなく家族の体も支える食事ですから。
レシピよりも自分の五感で作る
よく薬膳講座をしていると、『お料理教室ですか?』と聞かれます。
料理教室はしていません。座学のみにして、基礎的なことをしっかり
覚えてもらってあとは自分の感覚でやってください、という感じです。
自分の感覚を大切にしてほしいと思います。
小さじ何杯、何分加熱、とかではなくて、自分の感覚で
塩はこのくらいの塩梅、美味しそうな匂いがしたらこうして、
こういう音になったら火を止めて、
っていう五感的な感覚こそ、料理には必要では無いでしょうか?
感覚を養うこと
作り手の意識が大切だと思っています。薬膳の講座では
こういう季節や体質にはこういう食材が良いです、
というお話をしますが、季節や体のことをよく観察することも
学んでいきます。
単純に夏だから冷やしましょう、とかではなく、
夏の暑さにも色々ある。湿気が高い、暑さでバテている
暑いのに足元は冷えている、色んなことが起きる。
そういうことを『暑いから冷やす』という単純な知識(情報)ではなく、
自分がどういう状態か、を自分がまず自分で確認してみることが大切
だと思っています。
本当に暑いと感じているのか、疲れていると感じているのか、とか。
知識として学んだことを自分が体感して本当にそうだ、と感じたことを
やってみる。実際にそうしてみてどのように、自分が変化するのかを
確認したり、実感することから私がお伝えしたい『薬膳』の
学びがあります。
知識はそこそこでも実感すること、が大切かなと。
食材へのこだわりは置いといて、
自分が食材を選ぶところから
食べ物のエネルギーを感じて
それを使いきり、自分が実感する。
そして、それを家族に還元していく。
そして、食べた時に自分の体に入っていく感覚を
しっかり味わう。
何かをしながら食べるとそういう感覚が素通りしてしまって
せっかくの食べ物のエネルギーを味わえないですよね。
そこにいる人と『美味しいね』と味わう。
『食の大切さ』とはシンプルにそういうことなのでは無いかと
思っています。
野菜の美味しさがすごく味わえるだけでなく、カネマツさんの
お母さんのホッとするような優しいエネルギーが味わえるような気がします。
冬の講座は来月1月16日です
☆講座情報
☆食や体質、漢方についてのご相談の予約
遠方の方はFBメッセンジャーやskypeなどで対応させていただいております。
長野市以外の方でもご予約承っております。
2018/12/09
髪の毛の状態と体のサイン
髪の毛の状態と体のサイン
髪の毛の悩みって、男性、女性問わずあります。見た目にわかりやすい部分なので、気にしない方はいないかも
しれません。そのため、変化があると敏感に感じやすい部分でもあります。
漢方薬を服用して髪の毛に変化が出始める方がとても多いです。
漢方には気・血を補充するものがあるので、
エネルギーや栄養が行き渡ると髪の毛の状態が変化しやすくなります。
髪のパサつきは『血虚』
髪がパサついて、艶がないという方は『血』が不足気味の『血虚』という状態と考えます。
パサつく、だけではなく、毛が細くコシがない、という方も
当てはまります。
『貧血』とは違い、『血』は全身に栄養を運んでいる液体。
その栄養が不足している状態と、考えてください。
食べているのにな〜、と思われる方もいるかもしれません。
食べている内容が大切です。
炭水化物はエネルギーにはなりますが、『栄養』を運んでいる
『血』に変化するものはタンパク質が中心になります。
また、タンパク質だけでなくミネラルも必須。
髪の毛は『血の余り』で作られる、と考えます。
食べ物は赤色の多い動物性タンパクや、色の濃い野菜、
植物性タンパク、海藻類などを選ぶように心がけてみてください。
参考:『血というもの』
白髪は脱毛は『腎虚』
若くして白髪が・・・とか脱毛が・・・という方もいます。特に女性は出産時に抜け毛がひどくなったり、
産後に急に白髪が増えた、という方も実は多いです。
これは『腎虚』という状態になっていると考えます。
腎は生殖系の働きに関係するので女性は特に
月経時や出産前後に白髪、抜け毛が増えたりしやすくなります。
男性は8の倍数の年齢、女性は7の倍数の年齢を
目安にすると自分が白髪が増え始めた(る)年齢がおおよそ
見当がつきます。
若いうちに白髪が増えてくる・・・というのは『若腎虚』と呼ぶことがあります。
生殖系の働きにも関係してくるので、ホルモンの状態にも少し不安がある方と
考えることもあります。
食べ物では『黒い食材』をできるだけ選ぶように心がけます。
参考:『先天の精と人の一生』
『抜ける』というのは、毛穴を閉じる力がないため、と考えることもあります。
体が疲れやすかったり、疲れが溜まっている状態が続いた時に
食事が不規則になり、『血虚』という状態が重なったり、
寝不足や年齢的な『腎虚』が重なると、抜け毛とパサつき、抜け毛と白髪、
といったように髪の毛へのダメージも増えてきます。
また、ストレスが強いと頭皮が硬くなり、頭皮の血流が悪くなってしまい
栄養が行き渡らずに抜け毛も増えやすくなります。
色の濃い食材や黒いものを食べたり、早寝を心がけ、
頭部をマッサージしてあげる。なかなか、毎日それを心がけるのは
大変かもしれませんが(?)毎日の食事や生活習慣が
どんな状態かサインとして髪の毛は現してくれます。
自分の髪の毛の状態を観察する、というのも『自分を知る』
手がかりになりますね☆
2018/12/05
月経前後の不調と食べ物
月経前後の不調と食べ物
月経前後の不調が『あ〜、しんどい』
月経前になるとイライラしたり、落ち込んだり、不安感が強くなったり
また、疲れやすいのに眠れないといった精神的な面での変調や
頭痛や肩こり、のぼせ感、便秘、やたらと甘いものを食べてしまうという
身体的な変化に悩む人は少なくありません。
精神的な変化も身体的な変化も
どちらもある、という方もいるし、
どちらかだけれどその変化が大きくて
毎月、月経が来るのが憂鬱・・・という方もいます。
月に一度やってくるこの時期が
快適になれば、デトックス時期になるのですが・・・。
こう言った月経にまつわる心身の変化を
東洋医学的に見ていくと、一つの原因にたどり着きます。
月経の不調は『血』の不足である『血虚』が原因???
月経というのは子宮内膜が剥がれて出血する期間です。
つまり『血』が体から失われていく時期。
『血』というものは栄養を体の隅々まで届けている液体となります。
出血している時期は『血』が不足してきます。
また、月経前も子宮に血が集まっていきますので
もともと全身的に血が不足している『血虚』という状態になると
栄養の不足によって体の様々な場所で影響が現れてくる、と考えることができます。
*血虚は貧血とは違います。その人の身体に必要な血の量が足りていない場合には
血虚となります。
参考:『血というもの』
『不通則痛(ふつうそくつう)』という考えてあり、巡りの悪い場所には
痛みが生じる、という意味となります。
血が不足することで巡りが悪くなるため足が冷えたり、腰が痛んだり
月経痛も強く出る傾向があります。血の巡りが悪くなることを
『瘀血(オケツ)』と言いますが、瘀血が悪化していくと
子宮や卵巣に病巣を作ってしまうこともあります。
また、脳に十分な血が巡らないと頭痛だけでなく不眠、
イライラ・不安、動悸などと言った精神的な変化も生じてきてしまうことがあり
体の変化だけではなく、心の変化が大きな負担になってしまうことがあります。
さらに最近では血が不足してくることで全身的に乾いて
月経前になると喘息がちになったり、抜け毛が増えたり
ということをご相談される方もいます。
様々な異なる症状ですが、原因は『血』の不足から生じている、と考えます。
原因は何から?東洋医学的視点から
もともと子宮内膜症や子宮筋腫、卵巣嚢腫、など子宮や卵巣に
何らかの原疾患があり、出血量が多い方や周期が短め(25日以下)になると
全身的な血の量が不足していく期間が長くなり
心身の不調が長引いていくことがあります。
子宮や卵巣にトラブルがないか検査をしておくのも大切です。
その他には、ストレスや疲れなどがたまるとホルモンのバランスが
乱れてしまうことがあります。
これは東洋医学的には『肝』・『脾』・『腎』の三陰に関わることになります。
簡単に説明すると、
『肝』は血を貯蔵している場所であり、気の巡りに関与しています。
気の巡りが改善すると血の巡りも改善しやすくなります。
『脾』は食べたものから気血を作り出し、巡らせている。
『腎』は先天の精であり生殖系の働きを調整しています
寝不足は腎を、ストレスは肝を、慢性的な疲れや食のトラブルは脾を
それぞれ傷つけます。
月経前のトラブルを軽くするための食事と生活養生
東洋医学では日常生活や食事を見直すことが大切となります。
ホルモンのバランスを戻すためには
肝・腎の働きを助けてあげることが大切です。
つまり、肝に影響するストレスを緩和し、腎を補う『補腎』を心がける、
ということです。
まず、肝の働きを助けてあげるには・・・
ストレスを緩和する、ということなんですが、それを
余り意識しすぎないことをお勧めします。
それよりも、ストレスを緩和するためには
『香り』が有効であると言われています。ハーブティーや
アロマ、食事などに香りの良いゆずやシソ、ハーブなどを
入れるようにすると良いかと思います。
気の巡りが改善すると血の巡りも改善され、月経痛や
月経前の頭痛、イライラ、不眠などが緩和されやすくなります。
参考:『ストレスが溜まった時に』
『女性ホルモンとハーブ』
次に『腎』の働きを助けてあげる『補腎』
大切なのは早く寝ること、そして黒い食べ物をできるだけ
食するように心がけることです。
腎の働きが改善されてくると月経のサイクルが整いやすくなったり
月経前の喘息、物忘れ、浅い眠り、夜中のトイレ、集中力の低下
などを軽減しやすくなります。
参考:『立冬』冬の始まりと養生
『先天の精と人の一生』
最後に『脾』の働きを助けて食べるものからしっかり
『血』を補えるようにしていきたいところ。
ただ、『脾』の働きが弱い人が実はとても多い。
元々の体質的に食べれるけれど吸収が悪い、食が細い、
ということもあります。こういう方は地道にコツコツ
血を補うものを積み上げるように食べていきます。
食べているものによって脾(消化吸収の働き)が弱まっているケースも
あります。
・冷えたもの、生物
・甘いもの
・油っぽいもの
などが脾の働きを損なうものです。例えば冷えたもの+甘い+油→アイス
になりますし、甘い+油→クリームといった具合。
特に甘みが強くなると、エネルギー過多になるのでイライラしやすく
なりますので気をつけてください。
そして、最終的には普段から『血』を補うものを食事に取り入れていってほしいですが、特に月経前からその辺りを意識していくと良いかと思います。
・肉・魚を含め血の色の濃い動物性たんぱく質
・野菜も色の濃いもの
・黒い食材(黒豆・海藻・黒ごま・黒米など)
・高タンパクな大豆製品(高野豆腐、納豆・・子宮筋腫などがある方は要注意です)
・卵
できるだけ冷えた食事は避け、バランスの良い食事、が基本ということです。
生活養生や食事は毎日の積み重ねなんです。
一回の食事を変えたからといって変化するものではなく、コツコツ
積み重ねていくもの。ストイックにやりすぎず、心地よく
続けていってください。
そうして、少しでも月経前後の憂鬱さから解放される
女性が増えることを願ってます☆
ご興味のある方は講座のご参加や
カウンセリングをご予約ください。
2018/12/02
抹茶と緑茶の飲み分け
抹茶と緑茶の飲み分け
お茶の歴史
お茶は平安時代に最澄や空海などの唐へ渡った僧侶によって日本にもたらされたそうです。
そして、鎌倉時代になってから、禅僧の栄西が
新しい抹茶の茶法と茶種を中国から持ち帰り、
お茶文化が発展しました。
栄西は日本最古のお茶の本『喫茶養生記』を書いています。
そこには薬膳の基本である『五臓の調和』について
そして、その中でも『心』の負担を和らげる『苦味』の代表として
お茶を紹介しています。
お茶の栽培や製法についてまで書かれているそうです。
抹茶と緑茶の違い
碾茶(テンチャ)というお茶を粉末にしたものが抹茶で、煎茶(一般的に飲まれているお茶)を粉末にしたのが緑茶です。
そもそもの茶葉が違うということですね。
そして、碾茶は、よしずなどで日光を遮った茶葉を蒸した後に、
揉まずに葉の形のまま一枚ずつ乾燥させて、葉脈や茎を取り去ったお茶です。
日光を遮ることで、お茶の甘み成分や旨み成分のテアニンが多く含まれる柔らかな
茶葉になるそうです。
煎茶は日光を遮ったりはしないで育てるので
緑茶成分の代表カテキンが碾茶(テンチャ)よりもたくさん含まれています。
カテキンは、渋味が強いのでお抹茶に比べ煎茶は、苦くなっております。
テアニンは、お茶の甘味や旨味成分であるアミノ酸の半分以上を占めている
お茶特有の成分です。
リラックス効果がとても高いのだそうです。
最近の研究ではテアニンはストレスや緊張を緩和し、
睡眠の質を改善する効果も期待できるという報告もあります。
お茶にはカフェインが含まれ、覚醒効果がありますが、
テアニンには興奮を適度に抑える働きがあるため、
カフェインによる興奮が穏やかな作用にとどまるそうです。
一方、緑茶に多く含まれるカテキンは、緑茶の渋み成分の元です。
コレステロールの増加を防いだり、血糖値の上昇を防ぐ効果、
があるので生活習慣病予防になります。また、抗菌作用などがあり
様々な健康に良い、という研究結果があります。
この渋みの主成分のタンニンはタンパク質を凝固したり
鉄などと結びつきやすい特徴があります。
そのため、渋みが強くカフェインを含むものを
多く摂取することで胃が重く感じたり、痛みを感じたり
しやすくなります。
また、鉄剤などを服用している方は服用前後は
お茶やコーヒは控えるようにと言われています。
実は抹茶には鉄や葉酸、ビタミンCなどが豊富に含まれています。
渋みも少ないことから胃の痛みや貧血などが気になる方は
抹茶の方がコーヒーや緑茶などよりも
オススメかもしれません。
逆にダイエットや風邪予防をという方には緑茶がいいのかもしれません。
食事にはやはり緑茶が合いますね。
そしてお抹茶は、家でリラックスして
美味しい一杯を美味しいお菓子とともにいただくのが
良いかもしれませんね。

2018/12/01
12月の予定
12月の予定
今年もあと1ヶ月となりました。そして、平成最後の年末。
今年は非常に夏が暑く、体の消耗が著しく、免疫力が低下して
最近ではインフルエンザやノロウィルス、風疹などの集団感染が
流行っております。
出来るだけ、体を温め、食事もナマモノやお酒は控え
早めに寝るようにすると良いですが・・・
年末でなかなかそうはいきにくいかもしれませんね(笑)
意識はそのように持って、年末年始でも
羽目を外さないようにお気をつけください。
そして、今年1年、できなかったこともあるかもしれませんが
できたことも、変化したこともあったはず。
良い面を自分でも喜び、また、来年以降の
計画などを冬の間に考え巡らせてみてくださいね。
なつめやの12月の予定
水曜日定休日(5・12・19)・26日の水曜日はお店は開けます
・6・13日(木曜日)、17日(日曜日)
・20・21日は午前中休み・14時よりお店
・24日(月・祝)は午後はお休み
・28日午前のみ・午後よりお正月休みになります(〜1月4日まで)
イベント
・19・20・21日は味噌作り講座となります。
『糀からの黒豆味噌作り』
・陰陽五行オンライン講座:12月13日

好評の黒豆茶もノーマルタイプ、シナモン味が揃いました。
寒い冬に血の巡りやむくみ改善にオススメです☆
2018/11/28
気功をオススメする理由
気功をオススメする理由
気功、と聞くとなんだか怪しい・・・とか
なに?それ?なにやるの?って普通に思って当然のことと思います。
ヨガでもないし、太極拳でもないし・・・
『気』とつく時点でよくわかんない、ってなる。
身体の中に流れている『気・血・水』
東洋医学では体の中に流れているものを『気・血・水』で
考えていきます。
血・水は物質なので目に見えるのでわかりやすいです。
血の巡りが悪くなる、とよく言いますが、
ではその血を巡らせているのはなんですか?っていう話。
心臓はポンプです。
送り出している場所。
血管は流れている場所。
なにが原動力として心臓を動かしているのか?
を考えた時に、エネルギーがあって動かしている、となります。
そのエネルギーこそが『気』です。
『気』ってなに?
『気』があって初めて色々なものが動いたり、温まったり
ものが変化したり、維持したり、となります。
体を動かし、温め、代謝させ、維持し、守る。
当たり前のことのように体を動かせているのは『気』によるものと
東洋医学では考えます。
でも『気』って見えないわけです。
見えないけれど、感じることはできる。
話をしなくてもなんとなくこの人イラっとしているな、とか
この人なんとなく楽しそうだな、とか
表情だけでなくても、例えば電話口でもそういうことを
感じることはあります。
また、ある場所へ行くと気持ちがいいな〜と感じる事もあれば
反対になんだかぐったりする、という場所もある。
この人といると疲れるな、と思う事もあれば
この人といると元気が出るな〜とか。
『気』は見えないけれど私たちは無意識のうちに感じています。
見えないから『無い』ではなく、『感じ取ろうという力』、
意識が大切。
自分の中に『気』が今どんな状態なのか?というのを
感じるのはなかなか難しいのですが、
『気功』をして、自分の体の中の『気』の流れが良くなると
なんとなく自分の『気』の状態が感じれるようになってきます。
いい状態なのか、少し疲れている状態なのか。
そこすらわからなくなってしまっている人も多く、
病気になって初めて自分の体のことに意識を向ける
ということがあります。
自分の体や、『気』の状態を感じて、自分の活動をしていくというのは
自分の体を守り、健康を維持していく上では大切なことだと思うのです。
『気』と『血』の巡り
血の巡りを整えようと思う時、その血を動かしている
気の巡りを良くしてあげるとより効果的になります。
気が滞ったまま(気滞)ではそこには血の滞り(瘀血)ができやすくなってします。
何か不調が出た時『ストレスのせいかな?』と思うことが
あると思いますが、そのストレスこそが『気滞』。
ガンなども『ストレスが原因なのでは?』と思う人も
いるかと思いますが、はっきりした原因は西洋医学的には
わかりませんが、東洋医学ではやはり強い『気滞』と『瘀血』
がもたらしたもの、と考えることができます。
気功で『気』を巡らせて『血』を巡らせ、病気を予防する
『気』は温め、動かす原動力なので気滞になればその部分は冷えて、
血の巡りが悪くなり、病気を作る元になりかねなません。
『気』というものを自分の体において少し意識していくと
自分の体が疲れやすい、この部分が重たい、この部分が冷えるということを
気功をすることで『気』の巡りを整えることで改善していくことができます。
気功っていうのは『気』を体内に循環させるトレーニング、運動です。
気功をすることで見えないものが見えるようになるとか、
ハンドパワーで治すとか、そういうことではなくて
自分で自分の体の中に流れている気・血・水を循環しやすくするもの。
結果、身体の調子もいい、風邪もひきにくい、代謝が上がって体がポカポカ
体型を維持する、老化予防、などに役立つわけです。
マッサージや何かの治療を受けても
数日すれば体が元のように強張ってしまったりしては
なんども治療を受けないとならない。
気功は日々の積み重ね
もともと、私も鞭打ちを2度やっているので
首・肩がこわばりやすく鍼治療を週に1度は欠かせませんでした。
それを、自分でトレーニングして
体の調子を整えていくことができれば
それが一番なんじゃないかな?と思い、私は学ぶことにしました。
おかげで今では鍼治療はほとんど行かないで済んでいます。
気功は単純な動作のトレーニングです。
無心に行い、自分の体のエネルギーを循環させ、血の巡りを整え
自分の体をパワーアップさせるためのもの。
日々コツコツ積み重ねていくものです。
なつめやでは気功の練習会や講座などを通じて
自分で自分自身の体を整えて、病気の予防ができるんだ
ということを体感していただけたらと思っています。
ご興味のある方は是非、ご参加ください。
2018/11/26
黒豆と黒小豆の販売
黒豆・黒小豆の販売
今年もようやく収穫できた黒豆と黒小豆です。なつめや農園(といっても母がやっておりますが)で
無農薬で作っております。
毎年、試行錯誤しながら効率よく栽培するようになり
今年はあまり実が入らないな〜、と言いつつも
例年通りの収穫となったようです。
手前味噌ではありますが、ふっくら甘みのある豆だと思います。
黒小豆は私が宮古島へ5年ほど前に行った時に購入してきたのを
こちらで栽培し続けてきたものです。
2、3年前からようやく量が取れるようになりました。
宮古島の黒小豆はポリフェノールの量が
ブルーベリーなどよりも多いのだそうです。
なつめやが『黒いもの』にこだわるかと言えば
小豆や大豆に比べるとポリフェノール量が多く
その分、血の巡りが活発になり、また、むくみを取り除き
デトックス効果も高まる、女性にとっては
お役立ち食品だと考えるからです。
目の疲れやカスミ、肌荒れ、むくみ、便秘など気になる方に
おすすめです☆
美味しくコツコツ続ける薬膳の基本食材ですね。
我が家では10年近く毎日黒豆を食べています。
おかげさまで父親の持病を除いては概ね健康。
長く食べ続けてきて、やっぱり良い食材だなと
思うわけであります。
お正月のお汁粉やおせち用にぜひ。

なつめや 店頭で販売しております。
黒豆 200g 600円
黒小豆 100g 400円(計り売り対応)
毎年、好評で早くに売れ切れますので
ご希望の方は
natsumeya1@gmaiil.comにご連絡くださいませ☆
2018/11/23
陰陽五行講座は豊かさの学び
陰陽五行講座は豊かさの学び
四回シリーズで始めた陰陽五行講座です。
一回目 陰陽
二回目 五行/肝・心
三回目 脾・肺
四回目 腎
の予定ですが、各2時間の講座はあっという間に過ぎます。
人それぞれの体質や思考の癖、一年間の体の変化にも
ある一定の法則のようなものが見えてきます。
人は闇雲に感情の波がある訳でなないように感じます。
それに至る理由が必ずある、と思っています。
ただ、それをしっかり観察しないとその法則性がわかりにくいという事なんですが。
その観察が自分ではなかなか難しいこともありますし、自信がなかったりする。
自分のことが自信持ってわかります!なんていう人あまりいないように思うんです。
人のことはわかったように見えても、本当にはわからないこともありますし、
自分のことはなおさらわかりにくい感じがします。
自分の内側からのサインは外に現れている
表面に出ている部分と内側の自分すら気づいていない部分。
五行でみていくと身体のサインから、その人の内側の
世界が見えてくることがあります。
カウンセリングしていると現時点の体調不良だとしても
この方は命をかけて赤ちゃんを産んだんだろうな〜とか
なけなしの力を使って頑張っているんだな〜とか
この人は案外力があり、それをバネに頑張っていてその結果体が
こわばっちゃっているんだな〜とか感じます。
土台の力がどんな状態なのか?
その土台の上に五臓(内臓)がどんな状態にあるのか?を探ります。
自分の内側を知ることで自分を癒す
陰陽や気血水を含め五行の関係性からその人の身体の中を見ていきます。
そうしているうちに、その人が気づかずに抑えている部分や、
古い記憶の中で傷ついている臓腑があることに気づくこともあります。
家計的なことも含めてその人の身体を通じて
その人に受け継がれた『流れ』を感じることすらあります。
また、その人の表面に出ている症状や体質的なものから
いわゆるトラウマ的なことが浮かび上がってくる。
それはその人が気づいて癒していくしかないので
それを静かに見守り、心身の調和を図りながら
体調を整えていくお手伝いをさせてもらっている、という感じで
私は漢方薬を作っています。
自分の身体のことを知ることから健康は始まる
五行講座では自分で自分の内側を見ていく
キッカケ、入り口になればと思ってはじめました。
自分の体のことって血液検査で検査の結果から
健康か不健康かを測るだけでは不十分ではないかと思います。
検査していて、何もなかったのにある日
がん細胞が見つかった、なんて話はよく聞きますし、
しょっちゅう風邪をひいていて、それが健康であるとは言い切れないと。
また、メンタル面でも、どこからどこが
メンタルクリニックや精神科へ行くような対象になるか?
なんてわかりにくと思います。
そして、そこで受診しても果たしてそれが本当にそうなのか?
ということもわかりにくい。
自分の体、内側のことを興味持ち<
どうなっているのか?を少しでも理解し、
自分でできる対策をしていく手助けになればと思っています。
みんな違う身体をしているので、それぞれの人に合う食べ物があるし
合わない食べ物もあります。
つい食べてしまって体調が悪くなるものや
その反対に体調が悪くなると食べたくなるものもあり、
その傾向もどうしてそうなのか?ということがわかると
対策が立てやすくなります。
西洋医学の治療をしていたとしても、それと並行して
食事のことや生活のリズムを見直すことをしようと思う時
五行、五臓の学びはとても役立つものが多いのです。
昨日は『脾』と『肺』についての講座でした。
どの講座でも今年の夏のことを考えると今年の秋は
様々な感染性疾患が流行するよ、と言ってきていました。
これはあてずっぽうに言っているものではなく
五行の関係性からそうなるであろうと、予想していました。
そして、そのためにこういう予防方法があるから実践してみてくださいね、とも。
陰陽五行は豊かさと拡大の智慧
そうやって、自然のリズムや自分の体のことなどを
感じるままに、心地よく過ごしていく。
季節の移り変わりを感じて、それに心身が変化していく。
そのためにちょっとした知恵があると自分の心身が思っている以上に
自由になる。
自由になると、意識や世界が広がっていく。
古い知恵の学びは実は人生をより豊かに、拡げていくために陰陽五行
はあります。
また、来年もどこかで講座を開催できたらな〜と考えております。
2018/11/20
妊活中の食事・養生法
妊活中の食事・養生法
生活リズムを月経期や排卵期を意識して変化させていくと妊活にプラスに働きやすくなります。
病院で治療をされている方々には
なつめや でお話しさせていただいていますが、
はじめは中々ピンとこない方もいます。
そのうち、漢方薬などで体の調子が良くなってくると
生活リズムを意識せずに活動していると
疲れやすいな〜と感じやすくなるようで、
自分から色々と気を付けるようになる方が多いです。
さて、
妊活中の過ごし方は
1、月経期
2、低温期
3、排卵期
4、高温期
に分かれます。
どの期間にも共通して言えることは早寝を心がける、ということと
腹筋を鍛えておく、ということですが
それぞれの期間に気をつける生活リズムもあります。
1、月経中
月経期は出血中なので、激しい運動や汗をかくような事はしません。気血を消耗している時期なので休息を多めに取ったり
食事もタンパク質を多めにとるようにすると良いです。
また、決して、下半身を冷やさず、冷たいものなどは
摂取しないことを心がけてください。
参考:『デトックスを東洋医学的に考える』
2、低温期
この期間は卵胞が育ってくる時期です。月経期はあまり激しく動けない時期なので、気血を巡らせるためにも適度な運動やウォーキングなどを
します。特に卵巣にトラブルがある方は卵巣への気血のめぐりが
悪いと卵胞の発育が遅くなったり、スムーズに排卵しにくくなります。
しっかりタンパク質を摂りましょう。特に『潤う食材』と言われるような
*胡麻、松の実
*豆腐、牛乳、チーズ、ヨーグルト、豆乳
*小松菜、アスパラガス、山芋
*百合根、銀耳(白キクラゲ)、
*卵、うずら卵
*ホタテ、牡蠣、アワビ、カニ、イカ
*鴨肉、豚肉
などが代表的なものになります。イメージとしては少しクリーミーだったりぷるっと
したものがいいですね。
参考:『血というもの』
『秋の乾燥は甘酸っぱさで潤す』
3、排卵期
この時期は気血をしっかり循環させることで排卵させ、また、しっかり高温期にしていくように少しエネルギーが強目のものを
食事に取り入れたりすると良いです。(高温期の食材とかぶります)
軽い運動やヨガなどはしていただくと、より、気血が循環しやすくなります。
*血流を改善する食材:黒酢・青梗菜・ナス・蓮根・黒きくらげ・黒豆など
*気の巡りを改善する食材:らっきょう・みかん・カボス・ジャスミン・セロリなど
4、高温期
子宮内膜を厚くするために血が必要となります。レバー・動物性でも赤みの強い食材を選んだり、
色の濃い野菜(ほうれん草・人参・ブロッコリーなど)、
赤い果物(いちご・ぶどう)などを多めに摂り、血を補うようにします。
そしてさらに、エネルギーが高めになるように木の実(栗・クルミ・松の実)
や手に入る方は鹿肉や羊肉などもおすすめです。
また、過ごし方としてはこの時期は妊娠したかのごとく
ゆっくり過ごすこと!
妊娠判定が出てから気をつけるのではない、ということです。
病院で治療中の方もそうでない方も、高温期は
とにかく無理をしない。
この時期は受精するかどうか、着床できるかどうか
妊娠中の一番気血を必要とする時期です。
参考:『栗は身近な薬膳食材』
最後になぜ腹筋を鍛えておくことを進めるか?
ですが、腹筋が弱いと赤ちゃんが育つに従って
子宮が重くなり腹筋で引き上げきれず、子宮が
おりがちになります。
早産の予防にもなりますし、産後の子宮の回復にも
役立ち、次のお子さんの妊娠へつなげやすくなります。
腹筋の鍛え方としてはコアの筋肉をつけるのが良いです。
(ピラティスなどは役立つかと思います。)
なつめやに来ていただいている方には気功法を指導しております。
そして、一番大切なことはこれらのことを
真剣に取り組みすぎず、ストレスがないように
楽しくやっていただきたい、ということです。
妊活をしていると『ストレス』というのが一番よろしくないですし、
ストイックすぎて疲れてしまいます。
心地よいな〜という感じを心がけていただければと思います。
今回は妊活の過ごし方・食事を中心に書きましたが、
これはどの年代の女性にも役立つ情報かと思います。
特に乾燥しやすい方や貧血気味の方は2の低温期を
体が冷えやすい方は4、の高温期を参考に。
また、血の巡りが悪く静脈瘤ができたり肩こりが激しい、という方は
3の排卵期を参考にしていただくと良いです。
上記のものはあくまでも一般的なものになりますので
体質や治療法などにより養生法などは異なることが多く
自分に合う養生法などはカウンセリングしていただけたらと思います。
なつめやブログblog
month's schedule今月の予定
month's course今月の講座

 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ スケジュール
スケジュール
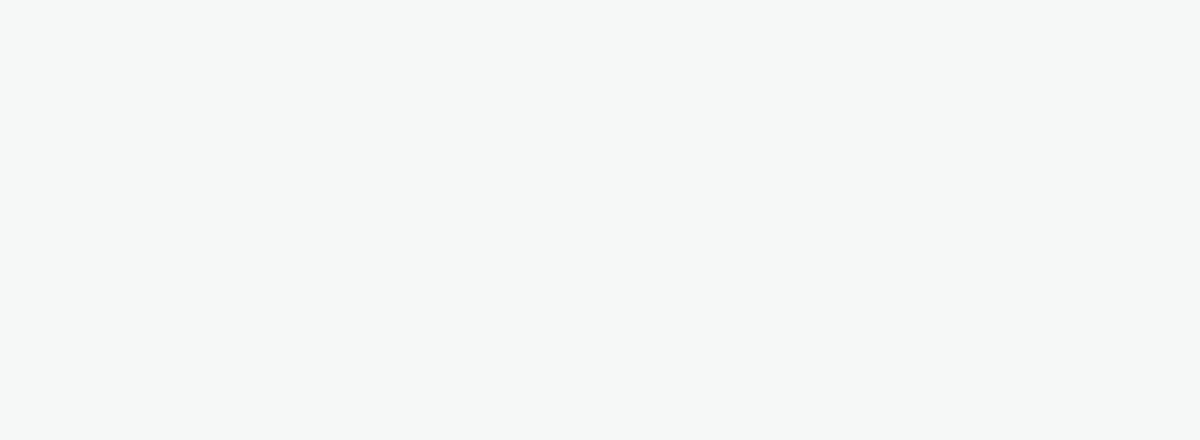

 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ Skypeでのご相談
Skypeでのご相談 スケジュール
スケジュール

