2018/12/21
黒豆味噌造りの全行程
黒豆味噌造りダイジェスト
12月19〜21日に糀造りからの黒豆味噌作りを行いました。
昨年までは松代のお寺の境内で、お寺の大きな鉄鍋で
助っ人を頼んで黒豆を煮て、買ってきた糀で味噌を仕込んでいました。
糀造りからを全て経験するというのは初めてです。
1日目:糀づくり
前日に洗っておいたうるち米を蒸します。
気持ち硬めと柔らかめの2パターンの炊き上がり。
麹菌は成田屋さんから原種の麹菌を分けていただきました。
薄い緑色の麹菌を炊き上がったうるち米を冷ましてからふりかけ
混ぜます。この時、少量の米に麹菌を混ぜた濃度の濃いものを全体の米に
投入するという方法にしました。うっすら色がついたかな、というくらいなので
糀が満遍なく行き渡っているのか心配しつつも、保温機へ入れて
発酵させ始めました。温度は35度前後。

2日目:糀の手入れ/黒豆を煮る
発酵器から糀を出して空気を入れるように糀をほぐします。
大した作業ではないですが、糀菌がついていて一安心。
さっさとやって保温器へ入れます。
今日のメインは黒豆を煮ること。
一昨日から水に浸しておいた黒豆を寸胴鍋で煮ます。
出来上がり100キロに対して前年よりも若干少なめの
22キロの豆を煮ます。
寸胴で煮ること2時間経つ頃に助っ人がきてくださり、
煮えかたを確認してもらうが、まだまだ、ということで
のんびり煮ます。
その間にパパッとおいしいおかずを作ってくださったり、皆さん
あれやこれやと色々と美味しいものを出してくれました
(自分は何も持ってこなかったことを悔やむ・・・・。)
途中でびっくり水を2回ほど入れてみました。
こうすると豆の皮と身が離れず、中の身までしっかり熱が入り
柔らかくなるのだそう。

3時間くらい経った頃、いい感じの柔らかさに煮上がる。
目安は親指と小指で豆が潰れるくらい。
食べた時に豆の皮の感触がほとんどなく、口の中ですぐに
潰れる感じがします。
このくらい柔らかくしておく、ということを忘れないようにしよう。
いつも人任せだったので良い勉強になりました。
3日目:いよいよ味噌造り
黒豆を少し温める、つもりがしっかり火入れをしてしまう。
しっかり火入れしなくても、少し温かいくらいでいいのに、
あれやこれやと段取りを話していたら豆が温まり過ぎた(笑)
糀を発酵器から取り出し、塩をまぶす。
ほんわか温かい糀。

豆を潰す機械でガンガン潰す。
夏に仕込んだときは皮が機械に目詰まりして大変だったのが
嘘みたいに快調に潰せる。
豆の煮方・柔らかさがこういうところで違いを生むんだなぁと
改めて気づく。
豆が温かすぎるのでうちわで扇いで冷ましてから
糀へ投入。混ぜる、混ぜる、混ぜる。
なんせ100キロ分なので作業台が小さく
作業しにくいのを皆さんの知恵を絞り
うまいことやっていただきました。

出来上がりは黒豆が若干少なめだったのにも関わらず、101キロの出来上がり!!
初めて自分たちで全行程をやりきり、上出来の仕上がり。
最低半年は寝かせますが、出来上がりが楽しみですね〜!
ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました!
2018/10/04
栗は身近な薬膳食材
栗は身近な薬膳食材
秋の味覚『栗』は身近な薬膳食材です。中国の甘栗も、日本の甘栗も。
栗は何と言ってもエネルギー『気』に働きかけていく食材です。
胃腸の働きを活発にし、下痢しやすい体質改善に役立ちます。
食べ過ぎると便秘になることも考えられますので
気をつけましょう。
温の性質なのでお腹が冷えて下痢をしやすい方に特に
オススメです。体の中を温めていくエネルギーですね。
つまり『陽』の性質が強いのが特徴です。
また、先天の精『腎』の働きを補う補腎食材でもあるので
老化予防、足腰の強化に役立ちます。
女性では冷えて高温期が安定しない方に良いですね。
栄養学的な部分を調べてみると亜鉛や鉄も含んでいます。
亜鉛はホルモン分泌や髪の毛、肌にも良い影響を与えてくれます。
実際、薬膳でも男性機能を活性化する食材としても
登場しています。
男性って案外、下痢っぽい方多いですよね。
薬膳としては鶏肉と炊き込みご飯にしたり、おかゆにしたり
というのが多いようです。
また、カリウムも多いので、むくみや高血圧にも
良いとされています。
薬膳的に考えると全て『腎』に繋がります。
ちなみに性質・性味/帰経は温、甘/脾・胃・腎となります。
成長・発育・生殖・老化の人の一生を支える『腎気』は
身近な食材でコツコツ養い続けることが大切。
1回食べたらどうなるものではなく、毎日無理なくコツコツ。
季節の栗はおこわにしたり、渋皮煮にしたりも良いですが、
本日は焼きポン栗。
水に一晩浸して、魚焼きグリルでしっかり目に焼けば
鬼皮も渋皮も剥きやすいです。
焼く前に栗の表と裏に包丁で切れ目を入れておくことを
お忘れなく☆

2018/08/31
夏の終わりに身体を調えておく(2)
夏の終わりに身体を調える薬膳その2
8月の終わりとともに台風が近づきすっかり涼しくなりました。
台風の低気圧はどのくらい9月にくるでしょう?
体が疲れてくるとエネルギーの巡りも悪くなり、
重だるさやめまい、食欲低下などが出てくることがあります。
前回の夏の終わりに身体を整える薬膳その1では
身体の熱をしっかりとって胃腸の働きを活発にし、
足湯をしながら夏の間に冷房で冷やした下半身は温めておきましょう
ということをお伝えしました。
具体的に
1、胃腸の働きを助け体力を増進、免疫力を強化する食べ物
(胃腸を丈夫にして肺の機能を高める)
干し椎茸(きのこ類)、栗、山芋(長芋)、キャベツ、ブロッコリー、じゃが芋、
かぼちゃ、さつま芋、里芋、いちじく、桃、米、もち米、きび、あわ、
いわし、さんま、サバ、うなぎ、牛肉、鶏肉、大棗(ナツメ)など。
圧倒的に穀物や芋類が多くなりますね〜。
雑穀はミックスされたものが手軽ですからそう言ったものを使うのもいいかと。
夏の疲れが胃腸に出ている方はお粥やキャベツをクタクタに煮込んだスープ
などをお勧めします。キャベツと玉ねぎをクミンやフェンネルを入れた
スープなどは胃が疲れている時などはとても美味しく感じます。
そして、一つのポイントとしては
香りのあるものを組み合わせてあげると食欲が増し、
消化も促され食べたものをしっかり栄養として吸収しやすくなります。
香りのあるものといえば、ハーブや紫蘇、ミョウガ、柑橘(ゆずなど)。
特に低気圧が来ている時などは気血の巡りが悪化しやすいので油は少なめにし、
カレー粉や生姜、ハーブを料理に使うと気血のめぐりが改善されやすくなります。
2、血を補い身体の中を潤していく
ほうれん草・小松菜・なつめ・梨・ブドウ(赤)・ブルーベリー・クコ・
イカ・タコ・豚肉・羊肉・レバー・マグロ・カツオ・卵・黒キクラゲ・
黒米・黒ゴマ・牡蠣・竜眼・キンシンサイなど。
特徴としては黒っぽいもの、赤っぽいもの、動物性のものでも色の濃いもの
となります。
(私は血が不足気味の体質なので黒米を白米に混ぜて夏の間は食べていますよ。)
薬膳では厳密に一つ一つの食材の特徴や帰経(どの臓腑に働きかけるか)を
細かくみていくことも大切かもしれませんが、ざっくりと大きな特徴を
覚えていくと良いと思います。
色や、香り、季節など五感からの情報で覚えていくといいですね。
一つの食材が本当に栄養学的にその栄養素を
十分に含んでいるかといえば採れた土地や、時期、肥料などによって
左右されます。
栄養学的にもこの食材はカロテンが多いとか、海藻ならミネラルが多い
とかそんなくらいにして、食材そのもののエネルギーを大切にした意識を
持たれた方がよろしいかと思います。
食べ物のエネルギーという視点と栄養素という視点は
似て非なるもの、と考えております。
実際に食べた時に体調が良いなとか、
胃がもたれず食べやすいな、ということを大切にして食べる。
どんなに栄養学的に良くても、自分が食べていて
胃もたれしたり、胃がスッキリしないようなものを
食べていては吸収しきれないと思うのです。
特に夏の終わりは冷たいものを飲食したり
夏野菜で胃腸が冷えて、疲れ気味。
食欲がないときは1食抜かすのも良いかと思います。
胃の調子を中心に考えて自分が食べて元気になるような食事で
調えていくといいですね。
カネマツ倶楽部さんの薬膳講座では
カツオ節+梅+シソ+ひじきの常備菜的なものを
ご飯につけていただきました。
家で作り置きしておくと胃腸の働きも活発になりますし、
気血が補われてなんとな〜くでも元気になるように
感じます。
毎日、少しずつの積み重ねていくものですから
美味しくて、簡単なものを取り入れていきましょう。
2018/08/21
デトックスを東洋医学的に考える
デトックスを東洋医学的に考える
デトックスとはdetoxificationの略語で、『解毒』という意味ですが色んな飲み物や食べ物の効果で謳われることが多いですが、
何を解毒する?ということを東洋医学的に考えてみると
また違う視点も出て来ます。
『解毒』ということは何かが溜まっていて、それを除去したい、
排泄してスッキリしたい、ということだと思うのですが、
何が溜まっているの?ってことです。
東洋医学では気・血・水のどれが滞っているのか?
ということを考えます。
単独・混合のどちらもあり得ます。
気が滞っているとき『気滞(キタイ)』と言いますが、
エネルギーそのものが流れず、溜まっているので
物体として血または水が同時に滞りやすくなります。
気+血の滞りを気滞血瘀と言いますがしこりや塊を作ることがあります。
女性だとやはり月経に症状が出やすく、月経痛や筋腫、膿腫などは
代表的なものです。
気+水というよりも水が滞ること自体が他の二つ、気・血の流れを
阻み、3種混合型になりやすく、これが実際にはとても厄介です。
水、そのものは冷たいものですから、そこに血・気も滞りやすく
ネバっぽい塊のようになってくるわけです。
俗にいうセルライト、中性脂肪・高コレステロールなどもこれに当てはまるかと
考えられます。
病理産物に繋がりやすい特徴があります。
ではその気・血・水の滞りをどうしたら除去できるの?
除去するというよりも『流す』が適切ですね。
1、冷やさない
2、動かす
が基本となります。
飲食物・衣類・住居環境において冷えた状態があれば巡りが悪化します。
いくらデトックスしても、冷えていると巡りが悪くなり再度、滞りができてしまいます。
そして、注意しなくてはならないのは『解毒する』排泄・発汗など
は、その後に体が冷えます。(汗をかいた後、お通じが出た後はスッキリしますが
ぶるっとすることがありますね。)
デトックスでは体を冷やさないようにしながら
老廃物を流していく、ということが大切です。
・気を流す→気の滞りはいわゆるストレスが原因ですからストレスを発散すること
自体が気のデトックスになります。自然の中へ行って良い気を
自然から取り入れるのも良いですし、
ヨガや気功など適度な運動などは無理のない気の流れを作り出します。
激しい運動をすると疲労がたまり、却って気が滞ってしまいますので
注意です!ストレスはためないように、と言っても大なり小なり
溜まるもの。
・血を流す→冷やさないこと+動かすで、やはり適度な運動が大切ですが、女性は
流す前に血の量が問題になります。貧血とは違い、東洋医学では
体に絶対量必要な血液が足りない状態を『血虚』と言いますが、
血虚になっていると、流れる量も少なく流れにくくなります。
そして、体型と血の量は比例しないこともあります。
太っているから血は足りているかといえばそうではないことも
あります。
血が足りているかどうかというのは例えば目をあっかんべ〜すれば
白っぽ人は不足気味ですし、赤っぽい人ならまずまず、といったところ。
食材では青魚などが血を補いながら巡りを改善してくれる食材となり
ます。サンマなど秋から旬となり、冷えていく季節に血が巡りにくく
なる時期に役立つ食材です。
例えば、サンマに大根おろしで黒酢をかけて食べれば血の巡りが
改善しやすくなる組み合わせです。
・水を流す→これは単純にむくみを取るだけでなく、水の塊も流すことを考えます。
ムクミだけならば豆類が良いのですが、いろんな豆があります。
体を冷やしやすい緑豆や小豆、冷やしにくい黒豆、となりますが、
それを甘く煮てしまってはNGですね〜。
秋からは体を冷やさないような黒豆茶がやはりおすすめとなります。
また、水の老廃物を出していく腎や膀胱を冷やすと水のたまりが
流れにくくなりますから腰周りは冷やさないようにすることです。
そして、水の塊を作り出しやすいような脂肪の摂取はなるべく
控えることです。脂というのは冷えれば固まります。糖分も
温かいと流れやすいですが、冷えれば固まります
冷たい+脂+糖=水の塊→病理産物に繋がりやすい、ということを
頭の片隅に入れて、そういった嗜好品の摂取をやめるだけでも
デトックス行為の一歩となります。
健康に良いと言われるような食事でもやってしまっていることが
あります。
何かを飲んだり、特別なことをしなくても
東洋医学的なデトックスはいつでもでるんですね〜。
ただ、それは日々の中でコツコツやっていくことだったりするので
はい!デトックスしました!という短期間の何か変化を感じる
ようなものではないですね。
ただ、振り子のようなもので急激なことをすると、反動も大きくなります。
それで戻ってしまうよりも、日々のデトックス、『流れ習慣』が
身についた方がいいのではないかな〜と思いますが・・・。
たまーに、ご褒美で美味しいものを食べたり、すると
幸せ感も倍増ですよ☆
日々の養生メルマガもご参考に☆
2018/08/19
先天の精と人の一生
先天の精と人の一生
両親から受け継いできた持って生まれた生命力そのものである『先天の精』、そして生まれてから後、摂取した飲食物から脾(消化器系)の働きに
よって作られる『後天の精』が腎に蓄えられて、成長や発育、生殖の土台となると
東洋医学では考えます。
この『腎』というのはいわゆる西洋医学的な『腎臓』の働きだけでなく
ホルモン分泌(生殖系)や中枢神経、内分泌、泌尿器など、様々な
生命の営みの中心となる働きをしているとされています。
先天の精は、後天の精でエネルギーを補充されて力を発揮して
いきます。また、後天の精を作り出すには先天の精が必要であり、互いに
依存しながらその人の生命力となっていきます。
両親からの受け継いできた先天の精が活発に動くには
食べ物の力(後天の精)次第というわけですね。
そのようにして先天の精・後天の精は腎に蓄えられ、
腎精もしくは精気と呼ばれます。
女子は7歳ごとに、男子は8歳ごとに腎の盛衰があります。
腎の力が弱いことを『腎虚(じんきょ)』と言い、
その力を補い、活発にすることを『補腎(ホジン)』
生命力そのものを活発にすることとなります。
腎の働きは様々ですが、生殖・成長・発達・老化と
受精卵から始まり、命を閉じるその時まで腎に蓄えられた
『腎精・精気』をよりどころに生きていく事になります。
今回は腎と脳に関することを書いて行こうと思います。
現存する中国の最古の医学書物である『黄帝内経』の『霊枢・経脈篇』には、
「人始めて生ずるや、先ず精をなし、精なりて脳髄生ず。」と書かれています。
男女の陰精の出会いで新たな命(精)が生まれ、その精から脳髄が生じる、
と考えられています。
男性と女性の精が交わるところから人の一生は始まり、その精は脳髄に
繋がっていく、という事になります。
また『髄海不足、則脳転耳鳴、脛酸眩冒、目無所見、懈怠安臥』
髄海である脳への精が不足すると、クラクラしたり、耳鳴したり、足腰がだるく
眼が見えにくくなって、やる気不足で横になってばかりいる、という
老化・認知症のことまでキッチリ書かれています。
先日の女性ホルモンとハーブ・漢方で書いたように西洋医学的には
視床下部や脳下垂体からは生殖に関するホルモンや甲状腺、プロラクチン、
副腎皮質刺激ホルモンなど生命に関するホルモンが分泌されています。
そういった観点からも腎と脳(髄)の関連は深いと言えます。
↑
このホルモン分泌は後日、また違う記事でも取り上げますが
とても大切な部分です。
そして、肝心なのは
『先天の精』は『後天の精』によって栄養を供給され
『精』となる、ということです。
持って生まれた資質は、食べたものに影響され、
それは脳・ホルモンにも影響するという風に解釈することができますね。
生殖ホルモンを活発にしたり、老化の予防になる
食べ物はどんなものが良いのか?
腎を補う食材は『補腎食材』と呼ぶことができます。
黒い色の食材・山芋・木の実・鹿肉・うなぎ・カツオなど・・・。
体にとって負担なく吸収しやすいものは山芋、になるかと思います。
鹿肉はとても体が温まりますが、逆に体が熱っぽくなるため
夏は避けたほうがよろしいかと思われます。
ジビエも時期を考えて食べることが美味しさにも
体への良い影響にもつながりますね。
木の実の栗・くるみも油が多いので食べすぎると胃もたれ
したりします。

薬膳というのは、良い面だけでなく、その反面も必ずある、ということも
意識して取り入れていただければと思います。
東洋医学の五臓・五行や気血精、陰陽の概念は
古い歴史の中で絶えず、いまに伝えられています。
今の時代に学んでも新しい視点と発見を
もたらしてくれる学問である、と学ぶほどに感じます。
どうぞ、ご興味あれば講座などにご参加ください。
なつめや講座情報
9
2018/08/15
視力回復と薬膳養生
視力回復と薬膳養生
先日メガネの耳にかける部分がポロっと落ちてしまい、出先ということもあって、しかもスペアのメガネがない!とすごく焦りました。
地を這いつくばってメガネの小さいネジを探し、なんとか
応急処置をしたもののぐらつく・・・。
購入したメガネ屋さんへ行くとすぐに直していただけました。
とは言え、スペアのメガネがないのが不安でもあり、
また、随分メガネを作っていなかったこともあり
新しいメガネを作ることにしました。
視力検査も久しぶり。
検査をしているとどうも様子がなんか違う。
終えたところで『視力がね・・・前より良くなっているんですよ。』
と言われ、びっくり!!念のため老眼も検査しましたが、
そちらの問題もないとのこと。
あれまぁ♪嬉しい♪
5、6年ぶりの視力検査でしたが視力が良くなっているというのが
自分でもなんでだろう?!と考えてみると
食べ物をかなり気をつけ出したこと、気功を始めたことなどが
理由かなと。(漢方はもちろんなので省く)
とにかく色の濃い野菜・黒いもの・クコはたくさん食べていましたし
夜も早く寝て血の消耗を抑えていました。
目の状態は血の状態と比例してきます。
こちらをご参考に→『血というもの』
自分では気づかなかったけれど身体の変化は少しずつしてきて
老化するどころかいい感じに回復してきているという、快挙。
他のお客様にも最近、健康診断に行ったら視力が良くなっていてね〜、
という方がいました。
コツコツ続けるっていうのは本当に気づかないところで変化をつけてくれます。
薬膳や気功に興味がある方は、どうぞ気軽に講座などにご参加くださいね。
→現在の講座情報
ブログで紹介していないことなどもインスタに載せていることが
あるので興味がありましたら是非フォローを☆
そして毎日、少しずつできる薬膳・養生メルマガもやっていますので
そちらもご登録くださいませ☆
なつめや 365日ちょこっと薬膳・養生メルマガ
ともあれ、新しいメガネが届き慣らし運転中。
今までのメガネはPoisonという名前でズバリ『毒』
薬も毒になるし、その反対もまた然り。
新しいメガネはLunorというドイツのメーカーさんの
ものです。スティーブ・ジョブスが愛用していたメガネも
こちらのブランドのものだそうで、ジョブスを目指します!
 ちなみにメガネは松本の『天下堂』さん。
ちなみにメガネは松本の『天下堂』さん。こちらも予約制です。
自分がいいかな〜と思うものとは意外なチョイスでメガネを
勧めてくださります。
お気に入りの、メガネは末長いお付き合いになります。
なつめやブログblog
month's schedule今月の予定
month's course今月の講座

 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ スケジュール
スケジュール
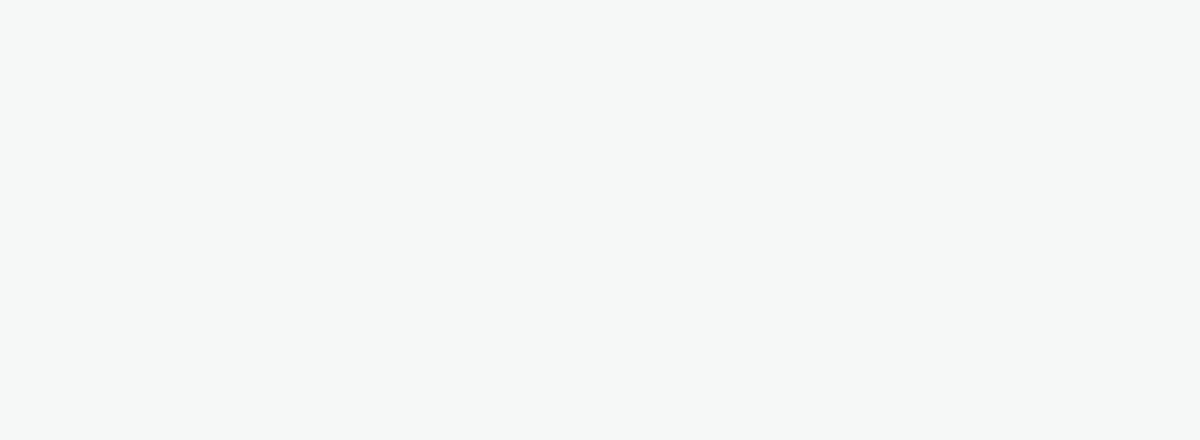
 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ Skypeでのご相談
Skypeでのご相談 スケジュール
スケジュール

