2018/11/10
風邪の漢方・養生
風邪をひいた時の漢方や養生
風邪には葛根湯、といつからかよく言われる様になりましたが実際は私はほとんど使うことがないです。
漢方薬局屋ですが。
葛根湯を飲んで風邪を改善させていくタイミングが大切です。
風邪の初期の初期にゾクゾクする〜という時に
飲んで、お風呂はいって(私は入ってしまう)、汗をしっかり
かいて風邪の症状を汗で散らす、ということができれば
成功です。高熱でガッと治すというのに葛根湯は使えます。
こういう手法を辛温解表、汗法と言います。
ただ、葛根湯が家にない時もありますから、そう言うときは
大量のネギを刻んでお味噌汁に入れて
一気に身体を温めます。お風呂も熱めのお風呂にさっと入って
汗が出始めたら上がり、お布団にくるまって汗をしっかりかくことです。
汗をかき始めたら栄養補給です。
すりおろしリンゴやはちみつレモンなどを頂くと
糖分や潤す作用のもので汗をかいて乾いてしまうと言うことは
防げます。
しかし、汗をかかせることができず、ぼーっと
熱っぽい症状が続いてしまうとそれはもう、体の中に風邪の
邪気が入り込んでしまっているので、そうなると葛根湯で
温め続けていると体力が消耗したり、喉が乾いてきて
空咳が出たりし始める。
そうなると、葛根湯ではないんですよね。
体の熱をとる様に潤してあげたり、
体力を上げていきながら熱を下げる様な漢方に
切り替えていきます。
今年は夏に汗をかいてだいぶ体の中が乾いている方が多いためか
風邪をひいて熱は取れたけれどいつまでも
喉がイガイガしたり、空咳が出てひどいと喘息気味になってしまって
という方もいます。
お腹を温めながら潤してあげるのが大切です。
食べ物でも蜂蜜やレンコン、アーモンドミルクなどで
肺を潤す食養生ができます。
乾いた咳が少しずつ痰が絡み始めたら潤いが出てきているので
肺を温め始めたりします。
その場合は背中にホッカイロ。
特に首の後ろを少し下がったところにポコっと骨が出ている
場所に『大椎(だいつい)』というツボがあります。
様々な邪気の出入り口になりやすい場所ですが
その辺りにホッカイロを貼ってあげると
肺も温まりやすく、風邪が改善しやすくなります。
普段も首・肩が凝りやすいと言う方はここに
小さめのカイロを貼っておくと良いです。
ただ、風はこじらせると大変なので、養生なんとかできる
体力のある方や、時期を読み間違えないことが大切ですね。
どの人にも養生法だけで治せるかといえばそういうことでも
ないですし、体力が消耗すると治りにくくなってしまいます。
また、小さなお子さんなどは熱が上がりすぎると脳に影響を
残しかねないので、早めの対処がとても大切。
風邪を引く、長引くということはそもそも体の免疫、抵抗力が
落ちているということですが、それは自分の体を守る
エネルギーが不足している、ということです。
睡眠をしっかりとり、体を温め、よく食べて
体のエネルギー回復をすることが大切なのは言うまでもありません。
今年は夏の影響が体に残っている人が多く
体が冷えていたり、乾いたりしているため
抵抗力が落ちています。インフルエンザやその他の風邪が
身体に入りやすい状態になっていますので
できるだけ日々の養生を大切にしてください☆
2018/08/23
体感と体質
体感と体質
自分の体質というのは案外自分は頭ではわかっているようでも実際の体のサインは違うよ、っていうこと結構あるんです。
暑がりで顔が火照って・・・と言いつつ、お腹は下痢気味だったり
腰が重だるかったりという方も、冷えからきてますよと
お伝えすると暑くないんですけど〜、とおっしゃる。
下半身が冷えるほど上半身に熱が上がってくるので
頭では暑い、と感じて実際は下半身が冷えていたりする。
また、ある方は『なんでも食べれるし、食欲がある』
と言いつつ、むくみがひどかったり、低気圧が近づくと
めまいがしたり、耳がふさがる感じがしたりという症状で
悩んでいる。
胃腸が弱いんです。甘いものと生もの、油は控えて、お腹温めてね、と
アドバイスすると『え〜、私胃腸は丈夫です』
な〜んてことになります。
食べれることは確かですが、食べたものを胃が消化し、
腸で吸収し、気血水の巡りが順調かというと
それができないので、むくんだり、そのむくみが原因で気血の巡りが
悪くなってしまう。
(胃腸の働きとむくみの関係はまた、いずれご説明します)
この二つの例は代表的なものですが、
一つ目の例では実際に自分が腰を温め、気功などで体を動かし始めたら
のぼせが取れたという方もいます。
温めてみたり、自分が体を動かすと気血水の巡りが改善し
それまでの『自分のぼせやすい』という体質ではなく、実は
『腰から下の冷え』『気血の巡りが下で滞っている』という
本来の体質改善ができるようになるんですね〜。
また、二つ目の例でも
食べ過ぎ、甘いもの・生もの・油っぽいものをやめ、
お腹・腰を温めるようにすれば良いわけです。
一旦食べ過ぎをやめるか、断食すると胃腸の具合が
わかりやすくなります。
台風前に体調が悪くなる方、低気圧が近づくと重だるくなったりする
方などは実は胃腸の弱さや。下半身の冷えからくることが多い。
どちらの例も普段の自分の感覚=自分の体質
と思ってしまっているのですが、
・普段動かしていない部分を動かす
・普段の食生活を見直してみる
ということをすると本来の体質が現れてくることがあります。
例えばズ〜っと冷えている方は『温かい』という感覚がわからないので
冷えていてもそれが当たり前、と思ってしまうかもしれません。
→こちらもご参考に
食べ過ぎ傾向な方であれば、胃の調子がものすご〜く悪くならない限りは
基本的には食べることが好きだったりするので、つい食べすぎてしまったり
多少、胃が重くてもこのくらいは大丈夫、と思うかもしれません。
食べ過ぎや食べているものを見直して胃がスッキリし始めると
それまでの胃の重さを感じることができるかもしれません。
普段の習慣や食生活などでそれが当たり前、と思っていることを
すこ〜し見直して、体の感覚を取り戻してみると
自分が気付かなかった自分の体質を発見できるかもしれません。
厳しい暑さの中で体の中から冷えてしまっていることがあります。
以前にオススメした足湯をぜひお試しください。
自分の体質って?
自分の体の状態を知って、生活の中で改善していきたい、という方は
ぜひ講座などにご参加ください☆
☆なつめやの講座

2018/08/21
デトックスを東洋医学的に考える
デトックスを東洋医学的に考える
デトックスとはdetoxificationの略語で、『解毒』という意味ですが色んな飲み物や食べ物の効果で謳われることが多いですが、
何を解毒する?ということを東洋医学的に考えてみると
また違う視点も出て来ます。
『解毒』ということは何かが溜まっていて、それを除去したい、
排泄してスッキリしたい、ということだと思うのですが、
何が溜まっているの?ってことです。
東洋医学では気・血・水のどれが滞っているのか?
ということを考えます。
単独・混合のどちらもあり得ます。
気が滞っているとき『気滞(キタイ)』と言いますが、
エネルギーそのものが流れず、溜まっているので
物体として血または水が同時に滞りやすくなります。
気+血の滞りを気滞血瘀と言いますがしこりや塊を作ることがあります。
女性だとやはり月経に症状が出やすく、月経痛や筋腫、膿腫などは
代表的なものです。
気+水というよりも水が滞ること自体が他の二つ、気・血の流れを
阻み、3種混合型になりやすく、これが実際にはとても厄介です。
水、そのものは冷たいものですから、そこに血・気も滞りやすく
ネバっぽい塊のようになってくるわけです。
俗にいうセルライト、中性脂肪・高コレステロールなどもこれに当てはまるかと
考えられます。
病理産物に繋がりやすい特徴があります。
ではその気・血・水の滞りをどうしたら除去できるの?
除去するというよりも『流す』が適切ですね。
1、冷やさない
2、動かす
が基本となります。
飲食物・衣類・住居環境において冷えた状態があれば巡りが悪化します。
いくらデトックスしても、冷えていると巡りが悪くなり再度、滞りができてしまいます。
そして、注意しなくてはならないのは『解毒する』排泄・発汗など
は、その後に体が冷えます。(汗をかいた後、お通じが出た後はスッキリしますが
ぶるっとすることがありますね。)
デトックスでは体を冷やさないようにしながら
老廃物を流していく、ということが大切です。
・気を流す→気の滞りはいわゆるストレスが原因ですからストレスを発散すること
自体が気のデトックスになります。自然の中へ行って良い気を
自然から取り入れるのも良いですし、
ヨガや気功など適度な運動などは無理のない気の流れを作り出します。
激しい運動をすると疲労がたまり、却って気が滞ってしまいますので
注意です!ストレスはためないように、と言っても大なり小なり
溜まるもの。
・血を流す→冷やさないこと+動かすで、やはり適度な運動が大切ですが、女性は
流す前に血の量が問題になります。貧血とは違い、東洋医学では
体に絶対量必要な血液が足りない状態を『血虚』と言いますが、
血虚になっていると、流れる量も少なく流れにくくなります。
そして、体型と血の量は比例しないこともあります。
太っているから血は足りているかといえばそうではないことも
あります。
血が足りているかどうかというのは例えば目をあっかんべ〜すれば
白っぽ人は不足気味ですし、赤っぽい人ならまずまず、といったところ。
食材では青魚などが血を補いながら巡りを改善してくれる食材となり
ます。サンマなど秋から旬となり、冷えていく季節に血が巡りにくく
なる時期に役立つ食材です。
例えば、サンマに大根おろしで黒酢をかけて食べれば血の巡りが
改善しやすくなる組み合わせです。
・水を流す→これは単純にむくみを取るだけでなく、水の塊も流すことを考えます。
ムクミだけならば豆類が良いのですが、いろんな豆があります。
体を冷やしやすい緑豆や小豆、冷やしにくい黒豆、となりますが、
それを甘く煮てしまってはNGですね〜。
秋からは体を冷やさないような黒豆茶がやはりおすすめとなります。
また、水の老廃物を出していく腎や膀胱を冷やすと水のたまりが
流れにくくなりますから腰周りは冷やさないようにすることです。
そして、水の塊を作り出しやすいような脂肪の摂取はなるべく
控えることです。脂というのは冷えれば固まります。糖分も
温かいと流れやすいですが、冷えれば固まります
冷たい+脂+糖=水の塊→病理産物に繋がりやすい、ということを
頭の片隅に入れて、そういった嗜好品の摂取をやめるだけでも
デトックス行為の一歩となります。
健康に良いと言われるような食事でもやってしまっていることが
あります。
何かを飲んだり、特別なことをしなくても
東洋医学的なデトックスはいつでもでるんですね〜。
ただ、それは日々の中でコツコツやっていくことだったりするので
はい!デトックスしました!という短期間の何か変化を感じる
ようなものではないですね。
ただ、振り子のようなもので急激なことをすると、反動も大きくなります。
それで戻ってしまうよりも、日々のデトックス、『流れ習慣』が
身についた方がいいのではないかな〜と思いますが・・・。
たまーに、ご褒美で美味しいものを食べたり、すると
幸せ感も倍増ですよ☆
日々の養生メルマガもご参考に☆
2018/08/19
先天の精と人の一生
先天の精と人の一生
両親から受け継いできた持って生まれた生命力そのものである『先天の精』、そして生まれてから後、摂取した飲食物から脾(消化器系)の働きに
よって作られる『後天の精』が腎に蓄えられて、成長や発育、生殖の土台となると
東洋医学では考えます。
この『腎』というのはいわゆる西洋医学的な『腎臓』の働きだけでなく
ホルモン分泌(生殖系)や中枢神経、内分泌、泌尿器など、様々な
生命の営みの中心となる働きをしているとされています。
先天の精は、後天の精でエネルギーを補充されて力を発揮して
いきます。また、後天の精を作り出すには先天の精が必要であり、互いに
依存しながらその人の生命力となっていきます。
両親からの受け継いできた先天の精が活発に動くには
食べ物の力(後天の精)次第というわけですね。
そのようにして先天の精・後天の精は腎に蓄えられ、
腎精もしくは精気と呼ばれます。
女子は7歳ごとに、男子は8歳ごとに腎の盛衰があります。
腎の力が弱いことを『腎虚(じんきょ)』と言い、
その力を補い、活発にすることを『補腎(ホジン)』
生命力そのものを活発にすることとなります。
腎の働きは様々ですが、生殖・成長・発達・老化と
受精卵から始まり、命を閉じるその時まで腎に蓄えられた
『腎精・精気』をよりどころに生きていく事になります。
今回は腎と脳に関することを書いて行こうと思います。
現存する中国の最古の医学書物である『黄帝内経』の『霊枢・経脈篇』には、
「人始めて生ずるや、先ず精をなし、精なりて脳髄生ず。」と書かれています。
男女の陰精の出会いで新たな命(精)が生まれ、その精から脳髄が生じる、
と考えられています。
男性と女性の精が交わるところから人の一生は始まり、その精は脳髄に
繋がっていく、という事になります。
また『髄海不足、則脳転耳鳴、脛酸眩冒、目無所見、懈怠安臥』
髄海である脳への精が不足すると、クラクラしたり、耳鳴したり、足腰がだるく
眼が見えにくくなって、やる気不足で横になってばかりいる、という
老化・認知症のことまでキッチリ書かれています。
先日の女性ホルモンとハーブ・漢方で書いたように西洋医学的には
視床下部や脳下垂体からは生殖に関するホルモンや甲状腺、プロラクチン、
副腎皮質刺激ホルモンなど生命に関するホルモンが分泌されています。
そういった観点からも腎と脳(髄)の関連は深いと言えます。
↑
このホルモン分泌は後日、また違う記事でも取り上げますが
とても大切な部分です。
そして、肝心なのは
『先天の精』は『後天の精』によって栄養を供給され
『精』となる、ということです。
持って生まれた資質は、食べたものに影響され、
それは脳・ホルモンにも影響するという風に解釈することができますね。
生殖ホルモンを活発にしたり、老化の予防になる
食べ物はどんなものが良いのか?
腎を補う食材は『補腎食材』と呼ぶことができます。
黒い色の食材・山芋・木の実・鹿肉・うなぎ・カツオなど・・・。
体にとって負担なく吸収しやすいものは山芋、になるかと思います。
鹿肉はとても体が温まりますが、逆に体が熱っぽくなるため
夏は避けたほうがよろしいかと思われます。
ジビエも時期を考えて食べることが美味しさにも
体への良い影響にもつながりますね。
木の実の栗・くるみも油が多いので食べすぎると胃もたれ
したりします。

薬膳というのは、良い面だけでなく、その反面も必ずある、ということも
意識して取り入れていただければと思います。
東洋医学の五臓・五行や気血精、陰陽の概念は
古い歴史の中で絶えず、いまに伝えられています。
今の時代に学んでも新しい視点と発見を
もたらしてくれる学問である、と学ぶほどに感じます。
どうぞ、ご興味あれば講座などにご参加ください。
なつめや講座情報
9
2018/08/17
女性ホルモンとハーブ・漢方
女性ホルモンとハーブ・漢方薬
いわゆる女性ホルモンとは、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)という二種類のホルモンです。もう少し今日は詳しく説明します☆
1、視床下部から性腺刺激ホルモン放出ホルモン(ゴナドトロピン:GnRH)が
が分泌されます。
2、脳下垂体前葉からは
・成長ホルモン
・甲状腺刺激ホルモン
・副腎皮質刺激ホルモン
・性腺刺激ホルモン:卵胞刺激ホルモン(FSH)・黄体形成ホルモン(LH)
・プロラクチン(催乳ホルモン)
など成長や発育に関する大切なホルモンが分泌されています。
3、性腺刺激ホルモンである卵胞刺激ホルモン(FSH)や黄体形成ホルモン(LH)が
卵巣に作用し、卵胞が発育し始め、エストロゲンが分泌されます。
エストロゲンにより子宮内膜が増殖し、受精卵を迎える準備が始まります。
卵胞が十分に発育したとからだが判断すると、LHの濃度が急激に高まり
(=LHサージと言います)、卵子は成熟し排卵、となります。
排卵後の卵胞は黄体となり、プロゲステロンとエストロゲンを分泌します。
プロゲステロンは体温を上げて厚くなった子宮内膜を、さらに受精卵が
着床しやすい状態にします。
ざっくり性ホルモンの分泌は3ステップに分かれます。
(今日の本題は香りのことなのでホルモンのことはまた後日書きます)
では、今日の本題『ホルモンとハーブ・漢方について』
アロマやハーブなどの『香り』の成分が鼻の粘膜に付着し、電気信号に変換され,
脳の内側にある「大脳辺縁系」という古い皮質に伝えられます。
(外側は大脳皮質)
ここは、食欲や性欲などの動物と共通した 本能に基づく行動 、喜怒哀楽などの情緒
行動や記憶に影響し、自律機能にも大きく関わっています。
大脳辺縁系の支配下にある視床下部(自律神経系)は大脳辺縁系に強いストレスが
あると大きく影響されます。
ストレスを感じるとイライラしたり食欲が異常に増したり、逆に低下したりするのは
大脳辺縁系・視床下部の働きによるもの。それを『香り』の効果で緩和できるということなんですね〜。
医療現場でもアロマが使われるようになりましたが、私たちも香りを嗅いだり
ハーブの香りを楽しんだりすると心が穏やかになったり、少し元気になるような
感じがありますね。
視床下部・脳下垂体からは生殖にかかわるホルモンや甲状腺などのホルモンが
分泌されているので、ホルモンの状態をアロマやハーブの香りなどで
調える、というのもオススメです☆
嗅いだ時に『いい香りだな』と感じることが大切。
このアロマはこういう働きで〜とかあまり考えすぎないことですね。
漢方薬も面白いもので『香り』がそれぞれの生薬によってだいぶ違います。
漢方薬に入るものには薄荷や紫蘇などがあり、厳密には後から煎じ液に入れて
さっと煮て香りを楽しむというものがあります。
(粉の漢方薬だったりするとあまりこういう変化を感じられないのは残念ですが)
『香り』を色々なもので楽しんで、女性ホルモン(男性ホルモンも!)活発に
しましょう☆
☆ハーブについて
2018/08/13
妊活休みと漢方
妊活休みと漢方の役割
『妊活』『不妊治療』もずーっと続けていると気持ち的に疲れるだけでなく身体も割と疲れているので、たまにはお休みするのも良いよ、というお話です。

毎月、排卵があるからと行って毎月受精できる卵子が排卵されるわけではなく
また、男性側の精子もいつでもエネルギー十分ってことはないんですよね。
1つの卵子が成熟して排卵されるには6ヶ月くらいかかり、その頃に体調を
崩していたり、すぐれない時期があったりすると卵子もエネルギー不足だったり
することがあります。
精子は3ヶ月くらいで変化すると言われていますが、やはり男性側もストレスや
体調、食事の内容などが影響されやすく、いつでも元気であるとは限らないわけです。
まだ病院へは行っていないけれどという方もなかなか、妊娠につながらないと
ストレスが溜まってきます。
また、病院での治療を行なっている方は病院へ通うこと自体もストレスになることもありますよね。
毎月の治療でホルモン剤を服用したり、一度に沢山の卵胞を採卵することは
自然な身体のリズムからすると大きな負担になり、生殖的な力が
十分に発揮しにくい状況を作り出しかねません。
積極的に病院で治療をしない時期が怖い、と思うかもしれません。
でも!あえて、少し休みを入れると良いですよ、と私は言います。
特に夏、今年は暑さも厳しくこういう時は夫婦揃ってそんなに体調万全!ってこと
は少ないかもしれません。そんな時は思い切ってお休み、と割り切り
ストレスを発散したり、リラックスできるように旅行へ行ったり、
という時期に当てつつ、身体の状態をしっかり調え治す時期にしてみると
良いかもしれません。
治療やこれからのことをあれこれ考えるより、気持ちがリラックスすることで
気血(エネルギーや栄養)の巡りが良くなります。
例えば漢方薬などでは身体の冷えや血の巡りを改善することだけでなく
生殖的な力を底上げするものもある。
また日々の食べ物で卵子や精子の質をあげたり、生活リズムを
少し変えるだけでも身体の回復力がグググ〜と上がってきます。
こういう時期って自分が妊活をする前に経験しておくと
産後に役立ち、産後の回復にも大きな差が出てきます。
そして、何よりも、自分の身体がこんな風に変わる!
気持ちの面でもこんな風になるんだ!っていうことを
経験してほしいですね。
結果が繋がらないことに焦りや不安を感じるよりも
変化していく自分に自信を持って妊活に向かっていく。
妊活に一番適しているのは春・秋と言われています。
体が疲れやすい夏や冷えやすい冬は思い切って体準備期間として
蓄えた力をしっかり発揮していく『妊活』をオススメします☆
2018/08/09
ダイエットと体質
ダイエットと体質
ダイエットの漢方相談はそれほどなつめやには多くはないのですが、漢方薬を飲んでいたら体重が知らない間に落ちていた、という
方々がおります。しかも、とっても食欲旺盛。
私自身も、近年稀に見る食欲で、よく食べていますが、
体重を気にすることがほとんどないです。
しかも、すごい運動して、とかではなく共通しているのは
漢方薬、または気功ということだけ。
気・血・水のどれかが流れが悪くなってもそこには
滞りが生じ、たまります。
気が滞る→ストレス→やけ食い(笑)
血の巡りが悪くなる→瘀血ができて固肥り
水が滞る→冷えて代謝が悪くなる
特に気の滞りは実体が無い分、瘀血や水の滞りと重なりやすく
溜まった部分に病巣を作ってしまうこともあります。
漢方薬では気血水の流れを整えますし、気功でも面白いことに
気血水の流れが整う。
飲むか動くかの違いですね。
例えば
瘀血+気滞→心筋梗塞、動脈硬化
水の滞り+気滞→高コレステロールまたは糖尿などなど。
ダイエットどころか病気までつくりだしかねない・・・。
特に夏は暑いと言って冷たいものを飲んだり食べたり、冷房で冷やしたり
と水の滞りが著しく、体は冷えた状態で代謝が落ちています。
そこへ秋風吹く頃は食欲が戻理、糖質の多い芋やかぼちゃが美味しくなる。
冷えたところに糖質は一番避けたい状態。
夏は暑いかもしれませんが、冷たいものをガブガブ飲食しすぎず
足湯などをして内臓の冷えを取ることが大切です。
体質改善をして、食べても体重が一定にキープできるような
代謝の良い体にするのは夏の過ごし方で変わってきます。
ダイエットといって食事制限したり、激しい運動する必要はなく
体の中の気血水の流れを整える。
そういうちょっとした積み重ねが『養生』です☆
メルマガではそう言ったことをご紹介しています。
ご興味ある方はどうぞご登録を☆→こちら
なつめやブログblog
month's schedule今月の予定
month's course今月の講座

 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ スケジュール
スケジュール
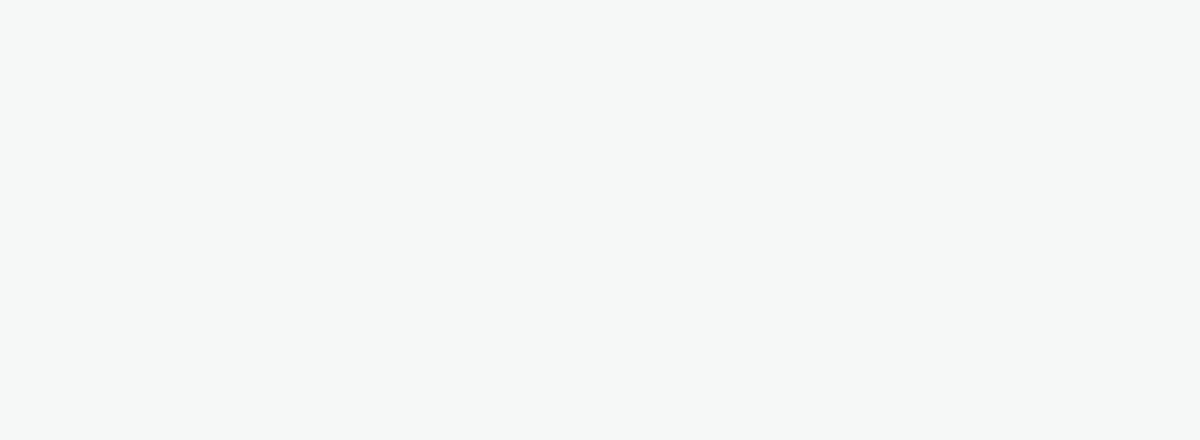
 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ Skypeでのご相談
Skypeでのご相談 スケジュール
スケジュール
